「SIerはなくなる」と言われる理由|活躍し続けるためにやるべきことを知ろう
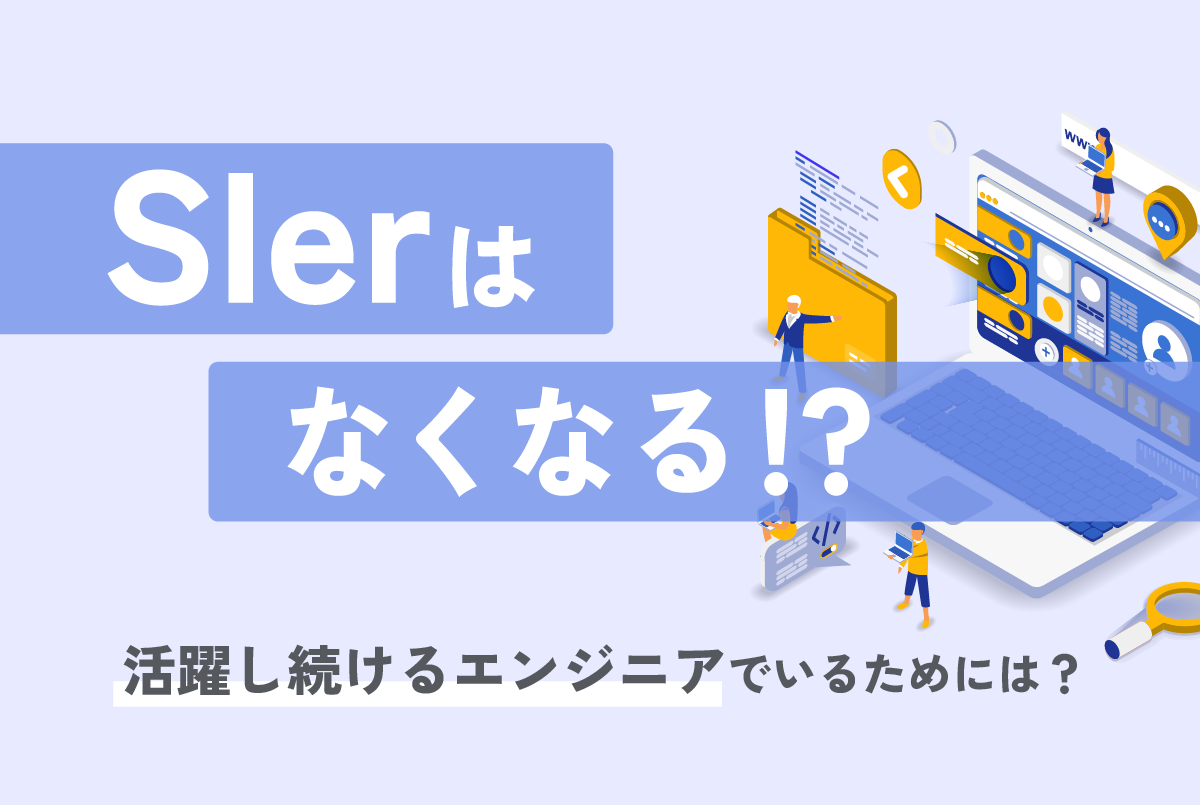
目次
近年、IT業界で耳にするのが「SIerはなくなる」という言葉です。
クラウド化の進展やDXの加速など、ITの潮流が大きく変わる中で、従来のSIerの在り方に疑問を抱く声も増えてきました。
確かに、旧来型のシステム構築や運用に依存してきたSIerにとっては、変化を求められる厳しい時代かもしれません。
しかし、SIerだからこそ担える役割や、今後も求められ続ける理由があるのも事実です。
本記事ではSIerは本当になくなるのか、現状や背景を整理しながら、これからの時代にSIerで活躍し続けるために必要な視点や行動を解説します。
今後のキャリア選択や働き方を見直す際の参考として、ぜひ最後までご覧ください。
なくなると言われる「SIer」とは?
SIerは、企業の業務課題を解決するために、システムの企画から開発・運用・保守までをトータルで支援する役職です。
プロジェクトの全工程を担う場合もあれば、他社と分担して進めることもあり、関わる範囲や役割は案件ごとに大きく異なります。
「SIerはなくなる」と言われる文脈でよく対象となるのが“独立系SIer”と呼ばれる企業で、下請け構造や価格競争の厳しさが課題となっています。
ここでは、SIerの役割をはじめ、各SIerについて比較し、解説します。
多様なSIerの特徴や違いを理解しておくことで、自身に合ったキャリアや今後の働き方を見極めるための重要な判断材料となるでしょう。
SIerの役割と仕事内容
SIerは、企業や組織の業務課題をITの力で解決するために、システムの導入・構築・運用を支援する役割を担っています。
業務内容は多岐にわたり、クライアントからのヒアリングに始まり、要件定義、設計、開発、テスト、導入、保守・運用といった各フェーズに関与します。
ただし、案件の規模や性質によっては、こうした工程の一部のみを担当することもあり、求められるスキルや対応範囲はプロジェクトごとに異なります。
そのため、SIerに求められるのは技術力だけではありません。
プロジェクトを円滑に進めるためのマネジメントスキルや、顧客と信頼関係を築くためのコミュニケーション力、折衝力といった、総合的なビジネススキルも重要となります。
以下の記事ではSESとSIerの違いについて詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
合わせて読みたい
SIerの種類
一口にSIerといっても、実はその形態にはいくつかの種類があります。
一般的には、以下の5種類に分類されます。
| 特徴 | 親会社 | 事業内容 | 企業の例 | |
|---|---|---|---|---|
| メーカー系 | 大手コンピューターメーカーから独立 | 大手コンピューターメーカー | 親会社やグループ会社のシステム開発 | 富士通 日立製作所 日本電気 |
| ユーザー系 | 大手一般企業から独立 | 大手一般企業 | 親会社または外部企業のシステム開発 | 伊藤忠テクノソリューションズ NTTデータ SCSK |
| 独立系 | システム開発を専門に行う | なし | 外部企業のシステム開発 | 大塚商会 オービック 富士ソフト |
| コンサル系 | 企画提案や要件定義を専門に行う | なし | 外部企業のコンサルティング業務 | 野村総合研究所 ベイカレント・コンサルティング シグマクシス |
| 外資系 | 海外を中心に事業展開している | 外資系企業 | 海外企業のシステム開発 | 日本オラクル アクセンチュア SAP |
「SIerはなくなる」と言われる文脈では「独立系SIer」を指すことが多いです。
理由としては、上流工程を担うことが少なく、下請け構造の中で価格競争や単価の圧縮といった課題にさらされやすいためです。
独立系SIerについては、以下の記事で詳しく解説しています。
自分に合うSIerも検討したいという方は、ぜひ合わせてご覧ください。
合わせて読みたい
「SIerはなくなる」と言われる8つの理由
近年では「SIerはなくなる」といった声も聞かれるようになりました。
その背景には、主に以下の要素があります。
- クラウドサービスが普及している
- 内製化・アジャイル開発が拡大している
- 多重下請け構造になっている
- グローバル展開されにくい
- 大口顧客へ依存している場合がある
- 労働環境に対するブラックなイメージがある
- エンジニアが不足している
- スキルを身に付けにくい
ここでは、以上の8つの視点を詳しく解説します。
1.クラウドサービスが普及している
近年では、企業が自社で物理サーバーを保有せず、AWS・Azure・Google Cloudといったクラウドサービスを活用するケースが一般的になってきました。
クラウドインフラの整備が進んだことで、専門的な知識がなくてもサーバーをスピーディーに構築・運用できる環境が整いつつあります。
これにより、IT基盤を社内で完結させる企業も増加しています。
特に、初期費用を抑えつつ、柔軟にスケーラブルな構成を取れるクラウドの特性は、多くの企業にとって魅力的です。
その結果、外部のSIerにインフラを委託する必要性そのものが薄れつつあります。
このような背景から、インフラ構築を主軸としていたSIerは、従来型のビジネスモデルを見直し、新たな方向性への転換を迫られるケースが増えています。
今後は、クラウドに関する高度な知識や、クラウド環境を活用した設計・最適化といったスキルが、SIerとしての競争力を左右する重要な要素となるでしょう。
2.内製化・アジャイル開発が拡大している
かつてはシステム開発を外部のSIerに委託するのが主流でしたが、現在ではユーザー企業が自社内に開発チームを設け、内製化する動きが進んでいます。
この背景には、アジャイル開発の普及があります。
アジャイル開発は、仕様変更やフィードバックへの迅速な対応を前提とした開発手法です。
従来のように全工程を外部に任せるウォーターフォール型よりも、柔軟性やスピードの面で優れています。
アジャイル開発が普及した結果、開発体制を自社内で完結させる企業が増加し、相対的にSIerに求められる役割が縮小しています。
3.多重下請け構造になっている
SIer業界は元請け・二次請け・三次請けといった多重下請け構造が一般的です。
このような階層構造では、クライアントから発注された案件が、いくつもの企業を経由して末端のエンジニアに届くことになります。
仕事が届く過程で中間マージンが発生するため、最終的に現場で作業するエンジニアの報酬が大きく削られてしまうケースが少なくありません。
そのため高い技術力を持つエンジニアでも、適切な評価や報酬が得られないという課題が生じています。
このような状況が問題視され、SIer離れにつながっているのです。
4.グローバル展開されにくい
日本のSIerは、国内の企業向けに特化したビジネスモデルを展開しており、グローバル市場への進出が難しいとされています。
日本特有の商習慣や顧客対応、受託型の開発スタイルに最適化されている点が、海外での展開を阻む要因です。
海外の企業ではシステム開発の内製化が進んでおり、アジャイル開発やDevOpsといった手法を活用して、自社で柔軟かつ迅速に開発を行う文化が根付いています。
こうした企業にとっては、SIerのように外部に業務を委託する形態そのものが馴染みにくく、ビジネスとして成立しにくいのです。
様々な事業のグローバル化が進む中で、世界を視野に入れた競争力を持つことは企業の持続的成長において欠かせません。
そのため、国内市場に依存し、グローバル対応力に乏しいSIerは、ビジネスの成長性や将来性に課題を抱える可能性が高いといえるでしょう。
5.大口顧客へ依存している場合がある
SIerは、システムの導入から運用・保守までを一貫して請け負える体制を持っていることから、大型プロジェクトを任されることも少なくありません。
そのため、自然と大手企業を顧客とすることも多いです。
安定した収益が見込める反面、こうした大口案件への依存が強すぎると、事業リスクが高まるという側面もあります。
顧客側の方針転換や事業再編などによって、プロジェクトの縮小や突然の契約終了が起きた場合、大きな打撃を受ける可能性があるからです。
また、顧客に意見しづらい関係ができあがってしまうと、無理な納期やコスト面での圧力が強まり、現場のエンジニアに過度な負担がかかる場合も見られます。
収益源を多様化し、リスクを分散させる体制を整えておかないと、変化の激しいIT業界において、生き残るのは難しいでしょう。
6.労働環境に対するブラックなイメージがある
SIerはシステムの企画から保守・運用まで幅広い業務を担うため、業務内容が多岐に渡り、一人当たりの担当範囲や負荷が大きくなりがちです。
厳しいスケジュールに追われる中で残業や休日出勤が常態化し、ワークライフバランスを取りづらい現場もあります。
また、SIerでは客先常駐のスタイルが多く、クライアント企業のオフィスで業務を行う場合もあります。
自社への帰属意識が薄れたり、上司や同僚との関係が希薄になったりと、キャリア形成やメンタル面での不安を抱える要因にもなるでしょう。
こうした背景から、特に若年層を中心に「ブラックな業界」というマイナスイメージを持たれることがあり、人材の確保や定着が難しくなっています。
実際に人材の流出や新卒採用も難航している企業もあり、業界全体の継続性や将来的な人材不足といった構造的な課題にもつながっています。
このような労働環境の改善は、SIerがこれからも価値を提供し続けるために避けて通れない重要なテーマだといえるでしょう。
7.エンジニアが不足している
DXや業務効率化の流れを受けて、あらゆる業界でITエンジニアの需要は高まっています。
しかし、その需要の高まりに対して供給が追いついておらず、日本のIT業界全体が慢性的な人材不足に陥っているのが現状です。
SIerも例外ではなく、プロジェクトの増加に対して人員の確保が追いつかず、常にエンジニア不足に悩まされています。
そのため、受託案件の品質が保てなかったり、納期に遅れが生じたりするリスクも高まっており、企業の信頼性や競争力に大きな影響を及ぼす可能性があります。
このような状況下では、新規案件の受注を抑えざるを得なくなり、事業規模の縮小や、リソースの再配分といった厳しい判断を迫られることもあるでしょう。
エンジニア不足の深刻化は、SIerにとって構造的な課題であり、今後の成長を阻む要因の1つと考えられています。
8.スキルを身に付けにくい
SIerの業務は案件によって、ルーティン化されたものやマニュアルに沿った単純作業が中心で、エンジニアとしてのスキルアップにつながりにくい場合があります。
特に運用・保守フェーズでは、既に整備された手順に従って業務を行うことが多く、最先端の技術に触れたり、自ら考えて改善を試みるといった経験を積みにくいです。
また、プロジェクトの一部のみを担当することが多いため、システムの全体像や上流工程に関わる機会が乏しく、経験を積むには限界を感じるケースもあります。
このような環境に身を置いていると、将来への不安を抱くことも考えられます。
結果的にWeb系や自社開発企業など、よりスキルが身につく環境への転職を考える人も少なくありません。
SIerは本当になくなる?残り続ける理由
近年ではSIerに対する否定的な声も増えつつあるのは事実です。
しかし、SIerの役割は完全に消えるわけではなく、重要性を増している分野も多いです。
業種・規模を問わずシステム開発のニーズは根強く残っており、SIerが果たすべき役割は拡大しているといえます。
「SIerはなぜ“残り続ける”のか?」という視点から、現在もなおSIerに求められている理由を整理していきます。
システム開発の需要はなくならない
IT化が進む現代において、業種や企業規模を問わず、システム開発のニーズは今後も着実に高まり続けると見込まれています。
業務効率化やDXの流れを受けて、ITシステムの導入・刷新は必要不可欠です。
一方で、すべての企業や組織が自社内に十分な開発リソースを持てるわけではありません。
中小企業や地方自治体など、IT部門が限定的だったり、専門人材を確保しにくい現場では、外部の専門企業に開発・運用を依頼するニーズは依然として高いです。
また社会インフラに関わる業務システムは、24時間365日安定して稼働し続けることが求められるため、信頼性と専門性を兼ね備えた開発体制が欠かせません。
このような高度かつ継続的なシステム開発・保守の需要は、今後も存在し続けるでしょう。
そのため、すべてのSIerが不要にはならず、むしろ社会的な役割を果たすSIerの存在価値は依然として高いと考えられます。
大型案件の受け皿として必要とされている
官公庁や大企業が手がける大規模なシステム開発プロジェクトでは、単なる技術力だけでなく、部門横断的な統合管理力や関係各所との調整力が求められます。
加えて、進行管理や品質保証、スケジュール調整といった工程を円滑に進めるためのノウハウが必要です。
このような高難度かつ広範囲に及ぶプロジェクトにおいて、中心的な役割を果たせるのが、豊富な実績と体制を持つSIerです。
SIerは、過去の経験を活かしながらプロジェクト全体を俯瞰し、技術面・業務面の両側から支援ができます。
一定規模以上の人員やリソースを短期間で動員できる体制を整えていることも、SIerならではの強みです。
複数のチームを束ねる管理能力や、エンジニアのネットワークを持っているからこそ、大口案件を支える存在として今後も必要とされ続けるでしょう。
DX推進によって需要が高まっている
企業の競争力強化や業務の効率化を目的として、DXに取り組む企業が急増しています。
この流れの中で、SIerは従来の「受託開発者」としてだけでなく「DX推進のパートナー」としての役割も担っています。
長年使い続けてきたシステムの刷新や、時代に即した業務プロセスの再設計の場面では、専門的な知識と実績をもつSIerに外部委託する企業が多いです。
こうした案件は、現状分析や改善提案といった上流工程から関与する必要があるため、SIerがコンサルティング的な立ち位置で支援する機会も増えています。
こうした背景から、DXをきっかけにSIerへの期待や役割はむしろ拡大しているといえるでしょう。
「2025年の崖」への対応が求められる
経済産業省が2018年に発表したレポートでは、既存のシステムの老朽化・複雑化・ブラックボックス化がもたらすリスクとして「2025年の崖」が提言されました。
2025年までに多くの企業が保有する既存システムが限界を迎え、刷新や再構築を行わなければ、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるとされています。
つまり、DXを阻む要因となっているシステムの刷新は、先送りできない課題といえます。
しかしIT人材は慢性的に不足しており、大規模なシステム移行や再構築をリードできる組織や人材は限られているのが現実です。
これまで多くの大型案件を手がけてきたSIerは、その実績と経験を活かし、企業の「2025年の崖」の突破を支援する重要なパートナーとして、今後も必要とされるでしょう。
オンプレミスの需要がある
近年はクラウドサービスの利用が拡大しているものの、金融・医療・官公庁などセキュリティ要件が非常に厳しい業界では、オンプレミス環境が今も根強く残っています。
これらの分野では、外部ネットワークと隔離された環境や、厳格なデータ保管基準を満たす構成が求められるため、パブリッククラウドの利用が難しいのです。
また、既存の業務システムとの互換性が必要な場合や、特殊なハードウェアを組み合わせる必要がある場面では、オンプレミスの方が適していることもあります。
こうしたニーズに応えるには、クラウドだけでなくオンプレミス環境に対応できる柔軟な技術力と対応力が必要です。
オンプレミス環境が存在し続ける限り、その構築・保守を担うSIerの役割もまた、確実に残り続けるでしょう。
業界特有のノウハウがある
SIerの強みの1つは、特定業界に深く根ざした業務知識と経験を蓄積していることです。
業界ごとに異なる業務フローや法的要件などを正確に理解しているSIerは、単なる技術提供者にとどまらず、企業の業務パートナーといえます。
たとえば、製造業であれば生産管理や在庫管理、金融業であれば厳格なセキュリティ基準や監査対応を熟知しています。
各業界や企業のルールやニーズを理解していることにより、適切な提案が可能です。
顧客との取引を通じて構築された信頼関係や、蓄積された業務ノウハウは新規参入企業では代替が難しい「現場を理解しているSIerならではの価値」です。
業界を深く理解し、業務課題の本質に踏み込んだ支援ができるSIerは、今後も多くの企業から必要とされ続けるでしょう。
労働環境が改善されつつある
これまでSIer業界は「長時間労働」や「客先常駐」などのイメージから、ブラックな職場環境として捉えられることがありました。
しかし、近年は働き方改革の推進により、労働環境の改善が進みつつあります。
リモートワークの導入や残業時間の削減などが取り組まれており、従業員のワークライフバランスの確保が重視されるようになりました。
「柔軟な働き方の促進」や「職場環境の改善」も今後の企業経営において不可欠な取り組みといえます。
他にも、エンジニアのスキルアップ支援やキャリア形成に力を入れる企業も増加し「技術者が成長できる職場」を目指す動きも活発化しています。
なくなると言われるSIerで活躍し続けるためにやるべきこと

SIer業界には構造的な課題もありますが、すべてのエンジニアが将来性を失うわけではありません。
むしろ、環境の変化に合わせてスキルや経験を積み重ねていけば、今後も活躍の場を広げていくことができます。
そのためにやるべきことを4つ紹介します。
幅広い経験を積んでおく
変化の激しいIT業界では、特定のスキルだけに依存することがリスクになるケースも考えられます。
技術のライフサイクルが短く、新しい開発手法やツールが次々に登場する現代では「1つの分野に特化していれば安心」という時代ではありません。
そのため、インフラ、開発、運用、テスト、保守といった多様なフェーズに積極的に関わることで、自身の視野を広げ、柔軟に対応できるスキルを身につけることが重要です。
たとえば、インフラと開発の両方を経験していれば、クラウド化やDevOpsなどのトレンドにも適応しやすくなります。
実際のプロジェクト現場では、技術力だけでなく、業務理解や関係者との調整力、プロジェクト全体の流れを俯瞰する力も求められます。
将来のキャリアの選択肢を広げるためにも、特定領域にとどまらず、幅広い現場での経験を積んでおきましょう。
スキルアップ・資格取得する
SIerとして長く活躍するためには、常にスキルを磨き続ける姿勢が重要です。
技術の進化が早いIT業界においては、現状に満足せず、新しい知識や技術を積極的に吸収しなければならないからです。
今後のSIerにとって特に注目すべき分野としては、以下のようなスキルが挙げられます。
- クラウド
- 自動化・仮想化
- IoT
- DevOps
- AI・機械学習
- UI/UX
これらはすべて、現代のITシステムに欠かせない要素であり、習得することで対応できるプロジェクトの幅が広がります。
ただスキルを習得するだけでなく「AWS認定資格」「基本情報技術者」といった資格を取得すると大きな強みになるでしょう。
「自分にはこのスキルがあります」と口頭で伝えるよりも、第三者機関によって証明された資格を保有していれば、社内外に対して自信を持ってアピールできます。
今後のSIerには、こうしたスキルと資格を通じて自身の市場価値を高めていくことが必要不可欠です。
マネジメントスキルを習得する
エンジニアとしてキャリアを伸ばしていくうえで、プロジェクト全体を俯瞰できるマネジメント力の習得は欠かせません。
技術力だけではプロジェクトを成功に導くことは難しく、チーム運営や進捗管理、リスクコントロールなど、マネジメントスキルが求められる場面が多いです。
特にSIerの現場では、クライアントを含む複数の関係者との調整が日常的に発生します。
要件定義のすり合わせ、課題解決のための合意形成、予算や納期の調整といったコミュニケーション能力は、上流工程での活躍に直結します。
チームメンバーのスキルや適性を見極め、適切なタスクを振り分けるリーダーシップや、人材育成に関わるマネジメント経験も重要です。
こうしたマネジメントスキルは、単なる技術者から「プロジェクトを成功に導くエンジニア」になるための鍵であり、高く評価されるスキルとなるでしょう。
転職する
SIerで働く中で「労働時間が長い」「技術的に成長できない」といった悩みを抱えている場合は、より良い職場への転職を視野に入れましょう。
近年では、働き方改革やDX推進の影響もあり、SIer企業の中でも労働環境や技術的な挑戦機会に力を入れている企業も増えています。
ひと口にSIerといっても、企業ごとに働く環境や事業内容、案件規模、重視する技術領域は大きく異なります。
現在の職場が自分に合っていないからといって「SIer全体が自分に向いていない」と決めつけるのは早計かもしれません。
まずは、自分のキャリアや働き方の希望を明確にし、他社の環境や制度と比較してみましょう。
SIer業界で長く活躍し続けるためには、現職にこだわりすぎず柔軟に選択肢を持つことが必要です。
監修者コメント
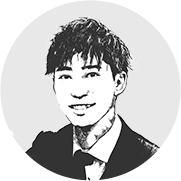
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
SIerからの転職はどのような職種に就ける?
SIerでの経験は、転職市場で評価されやすいです。
要件定義や折衝、ドキュメント作成、進捗管理といった上流工程のスキルは、プロジェクトマネージャーやITコンサルタントへの転職に有利に働くでしょう。
また、インフラや開発経験がある方は、以下のエンジニアへのキャリアチェンジも十分に可能です。
・クラウドエンジニア
・DevOpsエンジニア
・社内SE
・Web系エンジニア
近年ではDX推進に対応できる人材が求められているため、SIer出身者は「実務の幅が広い人材」として企業から重宝されます。
転職を検討する際は、自身の得意分野や強みを明確にした上で、キャリアの選択肢を広く捉えましょう。
なくなると言われるSIerについて、よくある質問
SIerという働き方に対して不安や疑問を抱えている人は少なくありません。
ここでは、特に多く寄せられる質問を取り上げ、SIerで働く上での向き・不向きや、キャリア選択の判断材料になるポイントを紹介します。
自身の適性や価値観と照らし合わせながら、今後の働き方を見つめ直すきっかけにしてください。
Q1.SIerをおすすめできないエンジニアっているの?
SIerは、人によって向き・不向きがあり、以下の特徴に当てはまる人にはおすすめとはいえません。
- エンジニア未経験・経験が少ない
- マネジメント系のスキルに興味がない
- 1つの分野で専門性を極めたい
- 新しいサービスの開発に関わりたい
この特徴に当てはまるなら、別のキャリアを選ぶことをおすすめします。
上記の項目だけでなく、自分の価値観や将来像なども広く考えてマッチしているかどうかを見極めたうえで、将来の方向性を検討しましょう。
詳しい解説は以下の記事で行っていますので、ぜひ参考にしてください。
合わせて読みたい
Q2.「SIerはつまらない」は本当?
結論「つまらない」と感じるかどうかは人それぞれですが、以下のような理由から、SIerの仕事を退屈に感じる人がいるのも事実です。
- 開発・プログラミングの機会が少ない
- 資料作成の業務が多い
- チャレンジが難しい
- 顧客に振り回されがち
- 技術面よりマネジメントスキルを重視される
「つまらない」という気持ちを放置したまま働き続けると、精神的なストレスが蓄積したり、将来的なキャリア選択に悪影響を及ぼす可能性があります。
少しでも違和感を覚えた場合は、自分にとっての“やりがい”を見直してみることが大切です。
SIerの働き方が合っていると感じる人にとっては、プロジェクト全体を俯瞰したり、顧客との折衝を通じてスキルを磨ける、やりがいのある職場でもあります。
自身のスキルや性格と嚙み合うかどうかを見極め、慎重に判断しましょう。
「SIerはつまらない」かどうかについては、以下の記事で解説していますので、詳細はそちらをご覧ください。
合わせて読みたい
まとめ
「SIerはなくなる」と言われる背景には、IT人材不足やクラウド化の進展、スキルの固定化といった業界全体の課題があります。
一方で、DX支援や「2025年の崖」への対応、オンプレミス環境の保守など、SIerだからこそ担える重要な役割が多いのも事実です。
つまり、SIerは形を変えながらも、これからも一定のニーズとともに残り続けていく存在だといえるでしょう。
そうした時代の変化の中で求められるのは「組織の変化を待つ」のではなく「個人が変化に対応できる力を身につけること」です。
スキルアップやキャリアアップを視野に入れ、自分自身の市場価値を高めていくことが、将来の選択肢を広げるカギになります。
もし、今の働き方に不安を感じているなら、まずは「SES企業で経験を積む」という選択肢も有効です。
SESであれば、プロジェクトを通じて多様な技術や現場に触れながら、着実にスキルアップを図ることができます。
実績を積んだのちにSIerへの転職を目指す、といったキャリアパスも選択できます。
私たちESESは、エンジニアが働きやすい労働環境をつくることを重視しているSES企業の1つです。
「案件選択制度」「単価評価制度」「高還元率」といった制度を整え、エンジニア一人ひとりが働きやすく、納得できる環境づくりに取り組んでいます。
あなたもESESで、自分らしい働き方と成長の機会を手に入れてみませんか?



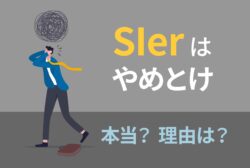
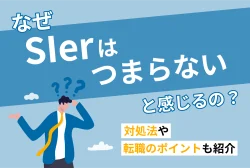


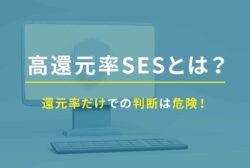
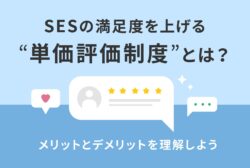
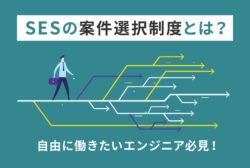
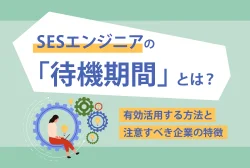


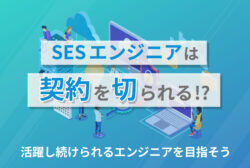
監修者コメント
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
プロフィールを見る
どのクラウドサービスを学ぶべき?
クラウドの知識を身につけるなら、最もおすすめなのはAWS(Amazon Web Services)です。
大きな理由は、国内外問わず導入実績が最も多く、エンジニアの求人市場でも圧倒的なニーズがあるからです。
実際、SIerが携わる多くの企業インフラもAWSベースで構築・運用されており、プロジェクトの主軸に関わるケースが増えています。
AzureやGoogle Cloudも学ぶ価値はありますが、まずは基本となるAWSから着手するのが最も効率的でしょう。
資格取得を目指すなら、まずは「AWS認定クラウドプラクティショナー」や「ソリューションアーキテクト・アソシエイト」がおすすめです。