インフラエンジニアに夜勤がある理由|夜勤の実態を理解して働き方を考えよう
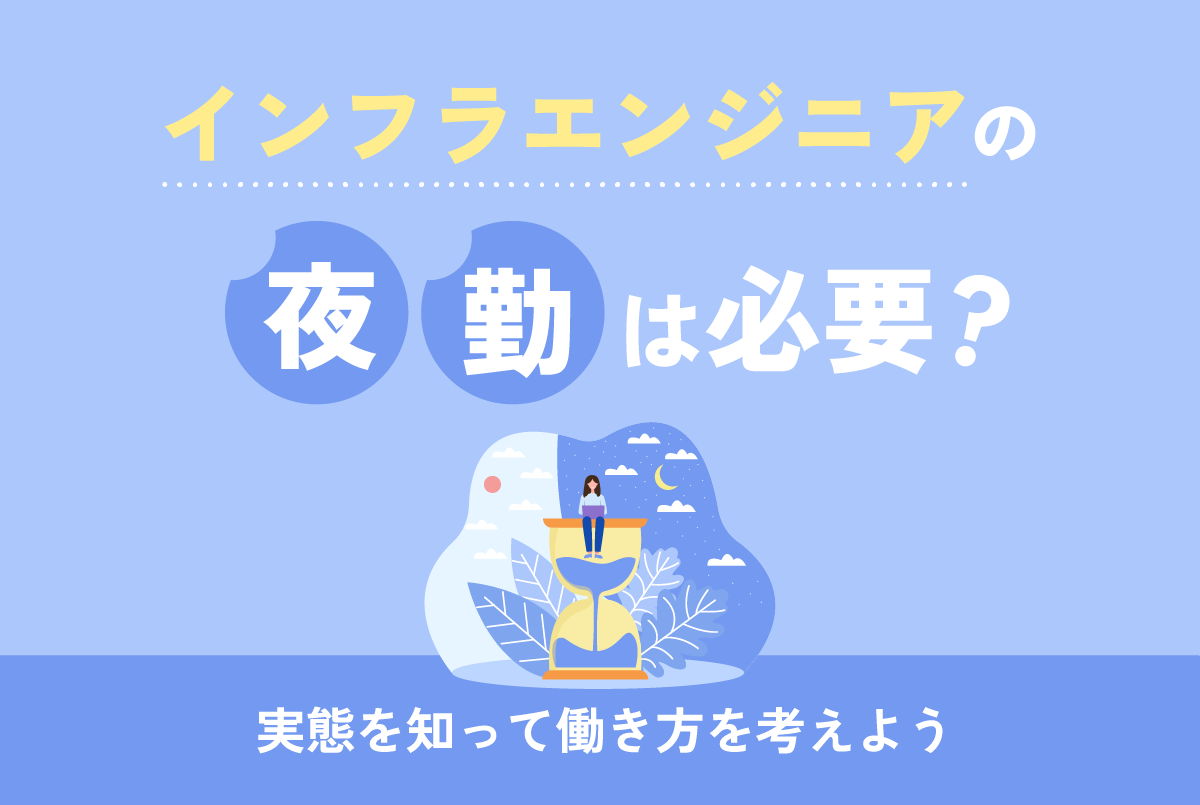
目次
インフラエンジニアとして働くうえで、夜勤は避けて通れないテーマです。
システムやネットワークは常に稼働しているため、深夜のトラブルにも備える体制が求められます。
夜勤と聞くと、体力的な負担や生活リズムの乱れを心配する方も少なくありません。
一方で、収入アップや日中の自由な時間を活かせるなど、夜勤ならではの利点もあります。
本記事では、インフラエンジニアに夜勤が求められる理由や、実際に働くうえでのメリット・デメリットを解説します。
夜勤の実態を理解し、自分に合った働き方を考える材料として役立ててください。
インフラエンジニアとは?
インフラエンジニアは、ITシステムやオンラインサービスを支えるために、基盤の設計・構築・運用を担当する職種です。
業務は「設計」「構築」「運用保守」の3つの段階に分かれており、それぞれに異なる役割とスキルが求められます。
まず、要件に基づいてインフラの構成やスペックを決定し、システムが安定して動作するよう全体の方針を固めていくのが「設計」です。
続いて構築では、設計書に沿ってサーバーやネットワーク機器の設定を行い、実際に環境を整備します。
最後の運用・保守では、監視を行いながら、障害対応やアップデート作業を通じて、安定稼働を維持します。
夜勤を取り入れ、24時間365日体制での対応をしている企業が多いです。
インフラエンジニアは、システムを裏側から支える重要な存在といえます。
インフラエンジニアに夜勤が求められる理由
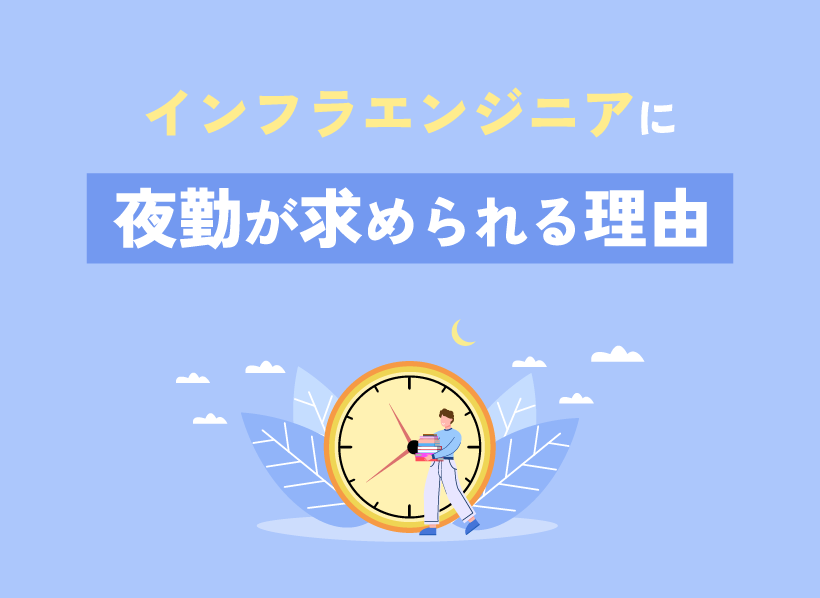
多くの企業では、インフラエンジニアに夜勤を任せる体制を採用しています。
その背景には、以下の3つの理由があります。
- 24時間365日稼働し続けるシステムがある
- メンテナンスやアップデートの必要がある
- 夜間のシステム障害や顧客対応をする
インフラを支える役割がある中で、夜勤での作業は欠かせないものといえます。
24時間365日稼働し続けるシステムがある
金融機関のオンラインバンキング、ECサイトの注文処理など、私たちの生活に密接に関わる多くのサービスは、24時間365日止まることなく稼働しています。
このようなサービスでは、インフラが停止すれば業務に支障をきたし、ユーザーにも深刻な影響を及ぼしかねません。
そのため、こうした業界では昼夜を問わず、システムの安定運用を目的とした監視や保守対応が継続的に行われています。
特に大規模なシステムやグローバル展開しているサービスでは、深夜でも利用されるため、常時監視が当然の運用体制として定着しています。
このような環境下では、シフト勤務を含めた人員配置が必要となり、夜勤が発生するのです。
メンテナンスやアップデートの必要がある
サーバーやネットワーク機器は、長期間安定して運用するために、定期的なメンテナンスやソフトウェアのアップデートが欠かせません。
これらの作業には一時的なシステム停止や通信断のリスクが伴います。
そのため、Webサービスや外部向けシステムでは、トラブルを避ける目的から、アクセスの少ない深夜帯に作業を行うのが一般的です。
社内向けの業務システムであっても、社員の作業時間を妨げないよう、夜間に対応を求められるケースが少なくありません。
インフラエンジニアにとって、こうした時間帯での対応は業務の一部と捉えられており、夜勤や待機体制を整える理由の一つになっています。
夜間のシステム障害や顧客対応をする
ITシステムにおける障害やアラートは、時間帯に関係なく突然発生します。
サーバーやネットワークが一時的にでも止まれば、サービス停止につながるため、即時対応が必要となります。
近年は自動復旧機能の導入も進んでいますが、すべてのトラブルが自動で解決できるわけではありません。
原因の特定や復旧方法の判断には、インフラエンジニアの知識と経験が求められる場面も多いです。
万が一に備えて夜間でも対応可能な待機体制を構築し、障害発生時に迅速な対応ができるようにしている企業も少なくありません。
こうした仕組みが、サービスの安定運用を支える大きな要素となっています。
インフラエンジニアに夜勤があるデメリット
インフラエンジニアの仕事では夜勤が必要ですが、その働き方には注意すべき点もあります。
インフラエンジニアに夜勤があるデメリットは、以下の5つです。
- 生活リズムが乱れやすい
- 体調に影響が出る場合もある
- 孤立を感じることがある
- キャリアアップにつながりにくい
- 家族や友人と時間が合わせにくい
人によっては大きなストレスや負担になるため、自身の体質や生活環境と照らし合わせながら働き方を検討することが重要です。
生活リズムが乱れやすい
夜勤を含む勤務では、日中に睡眠をとる生活リズムとなり、体内時計が乱れやすくなります。
慣れるまでに時間がかかるだけでなく、明るい時間帯の睡眠は遮音や遮光の工夫が必要となり、眠りの質が下がることもあるでしょう。
加えて、シフト制で勤務時間が変動する場合は、食事や入浴、就寝のタイミングも不安定になり、日常のルーティンが崩れがちです。
生活リズムが不規則になることで、自律神経のバランスが乱れ、疲労感や集中力の低下につながるという声も少なくありません。
このような状況が続くと、心身への負担が積み重なりやすくなるため、自分なりのリカバリー方法を見つけておくことが大切です。
体調に影響が出る場合もある
夜勤を長期間続けていると、生活リズムの乱れによって自律神経が不安定になり、体調不良を引き起こす原因となります。
日中に十分な休息が取れなかった場合、慢性的な眠気や倦怠感を感じるようになり、集中力や判断力の低下につながることも少なくありません。
若いうちは多少の無理がきいても、年齢を重ねるにつれて疲労が抜けにくくなり、夜勤後の身体の回復に時間がかかるようになります。
また、夜間勤務が続くことで食生活が不規則になり、消化器系の不調や免疫力の低下を招くケースもあります。
こうしたリスクを避けるには、定期的な体調チェックや適切な休養を確保する工夫が必要です。
孤立を感じることがある
夜勤では、日中よりも少人数で業務を担当するケースが一般的です。
チーム全員が揃っていないことが多いため、業務中のちょっとした会話や情報共有の機会が限られてしまいます。
些細な不具合であっても自分一人で判断を求められる場面が増え、精神的な負担を感じる人もいます。
また、すぐに相談できる相手が見つからない状況では、緊張感や孤独感が募ることもあるでしょう。
こうした環境では、技術スキルに加えて冷静な対応力や判断力も問われるため、自分の性格にも照らし合わせて選択する姿勢が重要です。
キャリアアップにつながりにくい
夜勤の業務では、システムの監視や障害対応など、あらかじめ決められた手順に沿った作業が中心になる傾向があります。
そのため、新しい技術やツールに触れる機会は少なく、スキルアップの実感を得づらいと感じるかもしれません。
一方で、IT経験が浅い人にとっては取り組みやすく、基礎的なインフラ知識やトラブル対応の力を身につける第一歩としては有効です。
ただし、定型業務が長く続いてしまうと、設計や構築といった上流工程に関わるチャンスが遠のいてしまいます。
技術の流れや広い視野を持ちにくくなり、キャリアの選択肢が限られてしまうリスクもあるでしょう。
将来的にステップアップを目指すなら、夜勤での経験を土台にしながら、段階的にスキルの幅を広げていく姿勢が求められます。
家族や友人と時間が合わせにくい
夜勤や不規則なシフト勤務では、日中を基準とした一般的な生活リズムとズレやすくなり、家族や友人との予定を合わせづらくなります。
休みが平日になる場合は、イベントや食事のタイミングが合わず、コミュニケーションの機会が減ることに悩む人もいるでしょう。
また、結婚や子育てといったライフステージの変化を迎えると、家庭での役割や時間の調整に負荷がかかりやすくなります。
さらに、夜勤明けの疲労感や体内リズムの乱れによって、せっかく予定が合っても心身ともに余裕が持てず、充実した時間を過ごしにくいことも考えられます。
ワークライフバランスを大切にしたいと感じる方には、大きなデメリットとなるかもしれません。
インフラエンジニアに夜勤があるメリット
インフラエンジニアの夜勤と聞くと、生活リズムの乱れや体調への不安といったネガティブな印象を持たれることが少なくありません。
しかし実際には、夜勤だからこそ得られる働き方の自由度や、経済面でのメリットも多いです。
インフラエンジニアに夜勤がある5つのメリットを解説します。
- 夜間手当てで収入がアップする
- 残業が発生しにくい
- 通勤のストレスが軽減される
- 平日の昼間に自分の時間をとれる
- 時間に追われず集中して作業できる
夜間手当てで収入がアップする
夜勤を担当すると、深夜手当や深夜勤務手当といった割増賃金が支給されるのが一般的です。
これらは労働基準法や各企業の就業規則に基づいて支払われるため、制度としてしっかり整備されているのが基本です。
日勤と同じ作業内容であっても、勤務時間が深夜にかかることでベースの給与に加算されるため、結果的に収入面でのメリットを得やすくなります。
キャリアの初期段階にある若手エンジニアや、スキルがまだ十分でない人にとっては、業務経験を積みながら収入を確保できる現実的な選択肢となるでしょう。
収入を重視したいフェーズにおいては、夜勤の活用が有効な手段となる場合もあります。
残業が発生しにくい
多くの場合、夜勤はシフト制によって運用されており、あらかじめ定められた時間内で業務を終える想定のもとにスケジュールが組まれています。
そのため、大きなトラブルが発生しなければ、定時で次の担当者に業務を引き継ぎ、そのまま退勤できるケースが多いです。
また、夜間帯は会議や突発的な業務の発生が少ないため、比較的落ち着いており、自分の仕事に集中しやすい環境といえます。
無理のないスケジュールで作業を進められることは、働きやすさにもつながるポイントです。
プライベートの時間をしっかり確保でき、日中よりも夜勤の方が予定のコントロールがしやすいと感じる人もいます。
こうした働き方を選ぶことで、自分のリズムを保ちながら安定した勤務を続けやすくなります。
通勤のストレスが軽減される
満員電車や渋滞による通勤ラッシュは、多くの人にとって大きなストレス要因となっています。
特に都市部では、移動だけで体力や気力を奪われてしまうと感じる人も少なくありません。
その点、夜勤であれば一般的な通勤時間を避けて移動できるため、混雑に巻き込まれる心配がほとんどなくなります。
空いている電車や道路を利用すれば、通勤時間を短縮でき、精神的な負担も和らぎます。
こうした余裕があることで、業務に集中しやすくなったり、コンディションを整えやすくなるでしょう。
通勤時のストレスが少ない環境は、安定して働くための土台として重要な要素といえます。
平日の昼間に自分の時間をとれる
夜勤明けや平日休みをうまく活用すれば、日中にまとまった自由時間を確保しやすくなります。
役所や病院といった平日限定の窓口に行きやすくなるため、有給休暇を消費する必要がありません。
混雑を避けて買い物や外出ができるなど、生活全体にゆとりが生まれるのも魅力です。
スケジュールの調整次第で学習や副業に取り組む時間も捻出できるため、充実した時間を過ごしやすくなります。
土日休みにこだわらず、あえて平日の静かな時間を大切にしたいという人には、夜勤というスタイルが合うかもしれません。
時間に追われず集中して作業できる
夜間はアクセス数や問い合わせが少ないため、日中よりも静かな環境が整いやすく、業務に集中しやすい時間帯です。
急な割り込みや打ち合わせが発生しにくく、自分のペースを保ちながら作業を進めやすいという利点があります。
そのため、落ち着いて仕事をしたいと考えている人にとって、夜勤は魅力的な選択肢になります。
また、普段は後回しになりがちな確認作業や手順書の見直しといったタスクにも、腰を据えて取り組みやすくなるでしょう。
企業によっては、業務の合間に学習や資料作成の時間を確保できることもあり、日々の仕事の中でスキルアップを図れるケースもあります。
こうした環境を活かしながら、自分の成長をじっくりと進めていきたい人にとっては、夜勤が向いている可能性が高いです。
夜勤があるインフラエンジニアに向いている人の特徴
夜勤を含むインフラエンジニアの仕事は、勤務時間や生活リズムの面から、誰にとっても働きやすい環境とは言い切れません。
ここからは、夜勤があるインフラエンジニアに向いている人の4つの特徴を具体的に解説します。
- 収入を重視したい
- 臨機応変に対応できる
- 機械やIT機器に興味がある
- 自己管理が得意
収入を重視したい
夜勤を担当するインフラエンジニアには、法律や会社の規定に基づく夜間手当や深夜割増賃金が支給されるため、同じ業務内容でも日勤より収入が高くなる傾向があります。
残業は発生しにくく、残業代による加算は少ないものの、手当込みの基本給で効率的に収入を得られます。
若いうちにしっかり稼ぎたいと考えている人や、生活費を安定させながら貯蓄に回したいと考える人にとっては、現実的かつ堅実な選択肢になるでしょう。
収入面でのメリットを重視する場合、夜勤は短期間で資金を確保したいタイミングやライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる働き方です。
臨機応変に対応できる
夜勤中のインフラ運用では、突発的な障害や予期しないアラートへの対応が求められる場面がしばしばあります。
このような状況下では、マニュアルに沿って動くだけではなく、現場の状況を把握しながら柔軟な判断を下す力が必要です。
深夜帯はサポート要員が少ないこともあり、自ら判断を下さなければならないケースも想定されます。
そのため、責任感を持って業務に向き合い、プレッシャー下でも冷静さを保ち続ける精神的な安定性が重要です。
変化への適応力が高く、想定外の事態にも前向きに対処できる人は、夜勤現場において重宝されやすい傾向があります。
機械やIT機器に興味がある
インフラエンジニアの仕事では、サーバーやネットワーク機器などのハードウェアに日常的に触れる機会が多く、機械やIT機器に興味がある人にとっては魅力的な職種です。
ただマニュアル通りに操作をこなすだけでなく、機器の構造や通信の仕組みにも関心を持てる人は、業務そのものにやりがいを感じやすいでしょう。
夜間は業務量が落ち着きやすく、自分のペースで作業を進められるため、好きな分野に没頭しながら経験を積める環境を好むエンジニアも少なくありません。
知識を吸収する意欲があり、技術そのものへの関心が高い人ほど成長しやすいといえます。
自己管理が得意
夜勤では生活リズムが不規則になりやすく、体調やメンタルのバランスを崩さないようにするためには、自分自身でコンディションを整える力が求められます。
食事・睡眠・運動といった基本的な生活習慣を安定させる意識があるかどうかで、夜勤の継続しやすさにも差が出てきます。
また、勤務外の時間をどのように使うかも重要です。
学習や副業にあてるのか、しっかり休息を取るのかを判断し、日々の行動をコントロールできるかが問われます。
こうした自己管理が得意な人ほど、夜勤という働き方を無理なく続けながら、目標に合わせたキャリア設計もしやすくなるでしょう。
監修者コメント
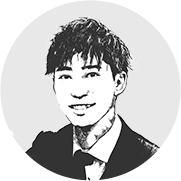
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
“孤独と判断”を前向きに楽しめる人は夜勤に強い
夜勤の現場では、サーバーの警告ログが上がる、VPN接続が突然不安定になるなど、予想外の事態が起こることがあります。
深夜ではこうしたトラブルに対し、チームリーダーやベテランにすぐ相談できるわけではありません。
自分の判断でログを洗い、手順書と照らし合わせ、必要なら緊急連絡を入れるかを決めなければならないからです。
この「すぐ相談できない環境」にストレスを感じる人もいますが、一方で「任されていると思うと頑張れる」と思える人は、夜勤にフィットします。
つまり、夜勤の適性は体力よりも“静かな緊張感の中で、自律的に判断・行動できるか”という特性に現れます。
日中のようなチーム連携よりも、一人で現場を守る責任感や冷静さにやりがいを感じるかどうかが、夜勤適性を見極めるカギになるでしょう。
インフラエンジニアの夜勤に関するよくある質問
インフラエンジニアの夜勤については、業務に関して様々な質問が寄せられます。
そのため、現場での実際の運用ルールや待遇、生活リズムとの向き合い方などをあらかじめ把握しておくことが大切です。
働き方のイメージをより明確にするための材料として、参考にしてください。
Q1.夜勤は避けられるの?
結論として、インフラエンジニアであっても、夜勤を避ける働き方は十分に可能です。
現場によっては、夜勤と日勤でチームを分けて運用しているケースもあり、日勤専属のポジションも一定数あります。
実際、求人や案件の中には「日勤のみ」と明記されているものもあり、勤務先の選び方次第で夜勤を避けられます。
また、設計や要件定義などの上流工程を担当するポジションでは、基本的に夜間対応が発生しないのが一般的です。
そのため、最初は夜勤があっても、キャリアを重ねていく中で離れていく道も選べます。
家庭の事情など、個々の状況に応じて夜勤免除の相談に応じてくれる企業もあるため、働き方に不安がある場合は、事前に相談してみるのも一つの手です。
自分のライフスタイルに合った働き方を実現するためにも、就業先の制度や体制をしっかりと確認しておきましょう。
Q2.インフラエンジニア以外でも夜勤はある?
夜勤が発生するのはインフラエンジニアに限らず、他のIT系職種でも見られる働き方の一つです。
例えば、セキュリティエンジニアはサイバー攻撃への即時対応が求められるため、夜間も監視体制を維持する必要があります。
また、テクニカルサポートやシステムエンジニアも、顧客対応や夜間作業が前提となるプロジェクトに関わる場合は、夜勤を含む勤務が組まれるケースもあります。
共通しているのは「昼間にシステムを止められない業務」を支える役割を担う職種であるという点です。
ただ、どの職種も企業によって夜勤必須ではない場合もあります。
夜勤を避けたい場合は、職種そのものだけでなく、企業の業態や運用スタイルも含めて慎重に選ぶことが求められます。
Q3.「インフラエンジニアはきつい」って言われたんだけど……
インフラエンジニアは「きつい」と言われることがありますが、それにはいくつかの理由が挙げられます。
急なトラブル対応が必要になることに加え、残業や休日出勤が重なる現場では、生活リズムが乱れやすくなるため、負担を感じやすいです。
また、常に新しい技術の習得が求められるため、学び続ける姿勢が不可欠です。
成果が表に出にくい仕事であることから、努力が評価されにくいと感じる人もいるでしょう。
さらに、単調なルーティン作業が多かったり、サーバールームなど冷えた環境での作業も発生するため、体力や集中力が求められる場面もあります。
こうした厳しさがある一方で、やりがいや専門性の高さに魅力を感じている人も多く、捉え方は人それぞれです。
合わせて読みたい
Q4.インフラエンジニアのやりがいって?
インフラエンジニアのやりがいとしてよく挙げられるのは、システムの根幹を支える業務に関われる点です。
大規模なプロジェクトでは、自分の手がけた構成が多くのユーザーに影響を与えることから、責任の重さとともに大きな達成感を味わえます。
また、クライアントや社内メンバーとの信頼関係を築きながら、幅広いスキルを習得できる点も魅力です。
設計・構築・運用といった各工程を通じて知識の幅が広がり、長期的かつ安定したキャリアパスを描きやすい職種といえます。
とはいえ、状況によってはきつさや大変さを実感することもあるため、自分にとってどのような価値があるかを見極める姿勢が欠かせません。
合わせて読みたい
Q5.インフラエンジニアに転職するには?
インフラエンジニアに転職するには、スキルや経験だけでなく、事前の準備が結果を大きく左右します。
まずはネットワークやサーバーに関する基礎スキルを磨き、実務レベルで扱える知識を身につけることが第一歩となります。
そのうえで、CCNAやLinuCといったインフラ系の専門資格を取得しておけば、スキルを客観的に証明でき、企業側からの信頼にもつながるでしょう。
あわせて、自分がどのような働き方をしたいのか、夜勤の有無や勤務地、チーム規模などの希望条件を整理しておくと、応募先を選ぶ際の軸になります。
さらに、職務経歴書の作成や面接対策も万全にしておくことで、スキルや志望動機をしっかりと伝えられる状態に仕上げておきましょう。
合わせて読みたい
まとめ
インフラエンジニアは、24時間365日止まることが許されないシステムを支える役割を担っており、夜勤が発生する企業も少なくありません。
夜勤は、夜間手当による収入アップや、落ち着いた環境で作業に集中しやすいといったメリットがあります。
しかし、生活リズムの乱れやスキルの偏りによるキャリア形成への影響など、注意すべき点があるのも事実です。
このように、夜勤を含む働き方はすべての人にとって快適とは限らず、適性やライフスタイルに応じて向き不向きが分かれやすい側面があるのです。
だからこそ、自分にとって無理のない働き方を考えましょう。
夜勤も含めてキャリアを前向きに築いていきたいと考える方には、SES企業での働き方も有力な選択肢の一つです。
ESESでは、柔軟な仕組みによって、一人ひとりのエンジニアが自分らしく働ける環境づくりに力を入れています。
例えば、勤務時間帯を含む希望条件に応じて案件を選べる「案件選択制度」を導入。
夜勤で収入を高めたい方も、日勤中心で生活リズムを整えたい方も、それぞれの価値観に合った働き方を選びながら継続的なスキルアップを目指せます。
さらに、単価評価制度や高還元率によって、成果に見合った報酬を得られます。
技術を磨きながら安定したキャリアと収入の両立を図りたい方にとって、実践的な成長が叶うフィールドとなるでしょう。
また、夜勤や日勤の希望はもちろん、働き方や将来のキャリアまでを見据えたサポート体制も整備しています。
働きやすさと成長機会の両方を大切にしたい方は、ぜひ一度ESESの募集要項をご確認ください。






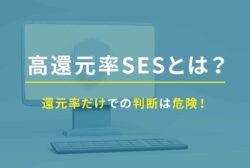
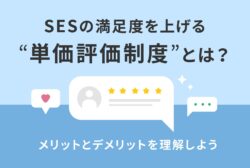
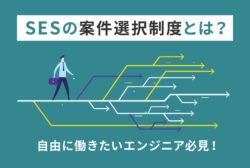
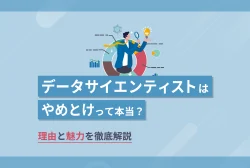
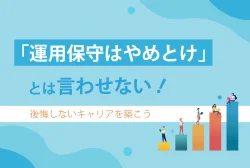
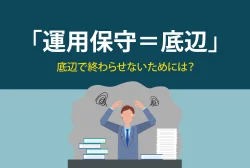

監修者コメント
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
プロフィールを見る
夜勤経験は「技術力」よりも「信頼力」を高めるキャリア資産になる
夜勤というと「生活リズムが不規則で大変そう」と感じる方も少なくありません。
しかし、夜勤の経験は単なる勤務時間の違いにとどまらず、将来のキャリアにおいて大きな信頼を得るきっかけにもなります。
例えば、深夜のシステム障害対応や、限られた人員によるインフラ保守などでは、冷静な判断力や正確な報告、決められた手順を守る姿勢が求められます。
夜勤の経験を積む中で、こうしたスキルが自然と磨かれていくのです。
日々の対応を誠実に積み重ねていくことで「あの人なら安心して任せられる」という信頼が、周囲の中に形成されていくでしょう。
インフラエンジニアという職種は、派手な成果よりも、安定した運用を支える姿勢が評価されやすい傾向があります。
その意味で、夜勤はトラブル対応の最前線に立つチャンスであり「責任ある立場を担えるかどうか」を周囲に示す機会でもあります。
「夜勤はしんどいし報われない」と感じたときこそ、自分の立ち振る舞いや日々の習慣が、どのように次のキャリアへつながるのかを考えてみてください。
そうした視点を持つことで、夜勤という経験が単なる通過点ではなく「信頼を積み上げるための武器」へと変わっていくでしょう。