入ってはいけないIT企業の特徴|見分け方・できることを知って自分に合う企業を見つけよう
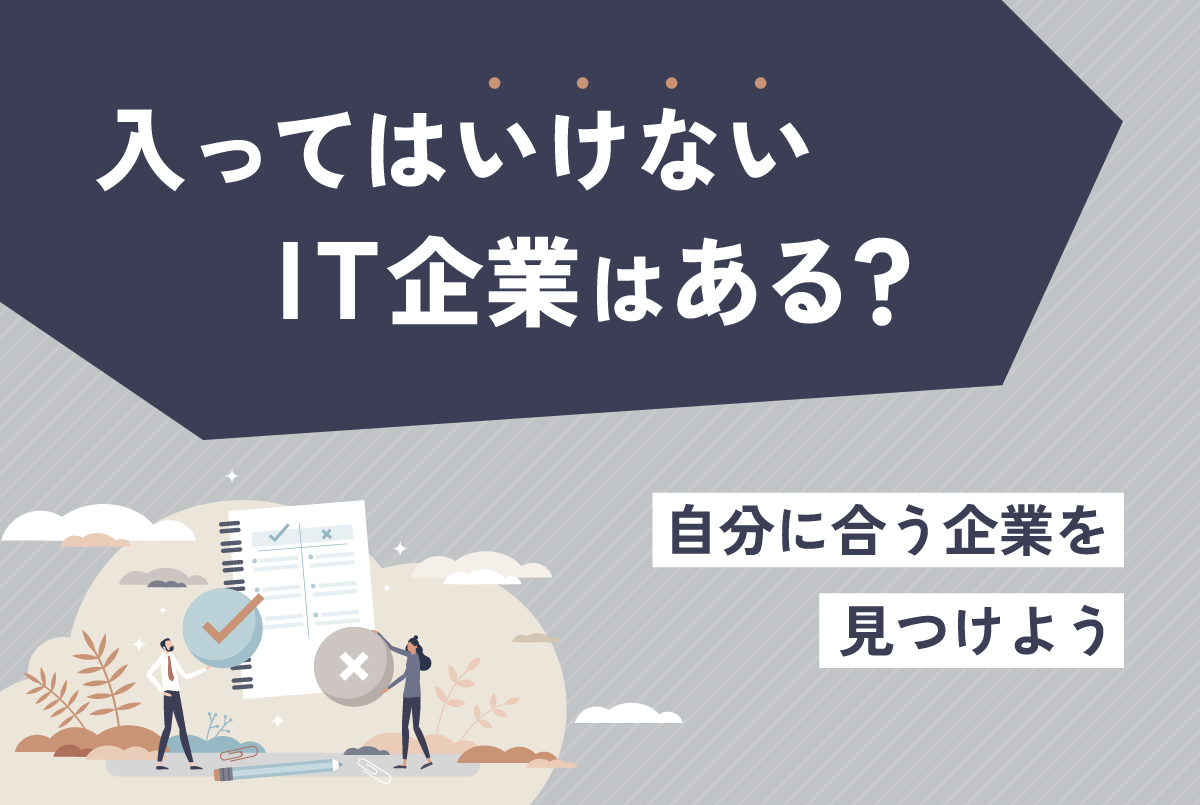
目次
年収を上げたいと思っているけど、ブラック企業には入りたくない。
このような思いを抱えながら転職活動をしているエンジニアの方も多いのではないでしょうか。
IT企業は会社によって、特徴や働きやすさに大きな差があります。
中には「入ってはいけない」と言われるような企業も存在しており、入社してしまうとキャリアが停滞したり、心身に悪影響を受けるおそれもあります。
「やっと転職できたのに、前職より環境が悪化した」
このような失敗をしないために、企業選びの段階で見極める視点を持つことが大切です。
本記事では、入ってはいけないIT企業の特徴を詳しく解説します。
自分に合う企業を見つけ、後悔のない転職を実現するために、ぜひ参考にしてください。
入ってはいけないIT企業に入るとどうなる?
入ってはいけないとされるIT企業に入社してしまうと、様々な影響が考えられます。
- スキルが身に付かない
- キャリア形成に悪影響を及ぼす
- 心身に不調をきたす
結果的に「転職したのに前よりつらくなった」と感じる危険性もあります。
スキルが身に付かない
入ってはいけないIT企業の特徴の一つに、スキルが身につきにくい環境があります。
例えば、毎日同じ作業を繰り返すばかりで、新しい技術に挑戦する機会がないままでは、エンジニアとしての成長が止まってしまいます。
また、業務が属人化している職場では、ノウハウが共有されにくく、自分しか対応できない作業に限定されてしまうでしょう。
その状態が続けば、スキルの幅が狭くなり、応用力や問題解決力が育たないおそれがあります。
さらに、業界や技術の最新トレンドに触れる場が少ないと、エンジニアとしての市場価値も下がっていく可能性もあります。
将来の転職やキャリアの選択肢を広げたいなら、常に学び続けられる環境かどうかを見極めることが大切です。
キャリア形成に悪影響を及ぼす
キャリアの方向性を自分で選べない環境に身を置くと、将来的に大きな壁に直面することになります。
例えば、入社後に希望していなかった職種へ突然配属され、そのまま異動の機会もなく経験を積むことになると、自分の意志とは異なる道でキャリアが進んでしまうでしょう。
スキルが思うように身につかない状態が続くと、キャリアの選択肢が狭くなり、本来自分が望んでいた仕事に就くことが難しくなります。
十分な実績や技術がないまま年齢だけを重ねてしまえば、いざ転職を考えたときにもアピールできる要素が少なく、選考を突破しにくくなります。
長期的に見て、計画的なキャリア形成ができない環境は避けましょう。
心身に不調をきたす
劣悪な労働環境に置かれると、心身への負担が蓄積しやすく、やがて深刻な不調を引き起こすことがあります。
長時間労働や頻繁な休日出勤が当たり前になると、十分な休息がとれず、慢性的な疲労や体調不良に悩まされることもあるでしょう。
特に、体調を崩しても空気感や人員不足の影響で休暇を取りづらい職場では、疲れはたまる一方です。
その状態が続けば、やがてメンタルにも影響が及び、うつや不安といった精神的な症状に発展するおそれも否定できません。
モチベーションを維持することも難しくなり、キャリアどころか日常生活にも支障が出てしまうかもしれません。
安心して働ける環境でなければ、長期的な成長を望むのは難しいでしょう。
入ってはいけないIT企業の特徴10選

IT企業と一口に言っても、その働き方や価値観、文化には大きな違いがあり、人によって合う・合わないは当然あります。
ただし、多くのエンジニアが「入るべきではなかった」と感じる企業には、いくつかの共通点が見られるのも事実です。
ここからは、入ってはいけないIT企業に共通する10の特徴を紹介します。
- 給与が極端に低い
- 単純な作業ばかりやらされる
- 多重下請け構造の下層の仕事しかない
- 長時間労働が常態化している
- 管理体制が整っていない
- ハラスメントが横行している
- 教育体制が整っていない
- 福利厚生が充実していない
- 離職率が高すぎる
- 募集要項に具体性がない
転職を後悔しないためにも、自分に合う会社かどうかだけでなく、業界で避けるべき企業の特徴を押さえておきましょう。
1.給与が極端に低い
給与が極端に低い企業では、働いても生活が安定せず、長期的なキャリア形成にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
業務量や労働時間に見合った報酬が支払われず、成果を出しても昇給幅が小さいと、努力が報われにくくモチベーションも続きません。
また、基本給が不当に低く設定されており、残業を前提にしないと十分な収入を得られないケースもあります。
賞与がなかったり、年俸制という名目で残業代が実質支払われない契約になっていたりと、給与体系にも注意が必要です。
求人情報の年収例やモデルケースが曖昧な場合もあるため、事前に細かく確認しておくことが欠かせません。
2.単純な作業ばかりやらされる
単純な作業ばかりを任される職場では、成長できない可能性が高くなります。
例えば、コーディングやテストといった定型業務を繰り返すだけで、新しい技術に触れたり、要件定義や設計といった上流工程に関われる機会がない場合です。
そのような環境では、誰でも代替可能な業務に偏りがちで、市場価値も上がりにくいです。
また、スキルアップを前提とした配属や指導体制が整っていない場合、自分の意志とは関係なくキャリアが止まってしまう可能性も否定できません。
新しいことに挑戦できるかどうかは、企業選びの大切な判断基準になります。
3.多重下請け構造の下層の仕事しかない
多重下請け構造の下層に位置する企業ばかりで働いていると、スキルアップやキャリア形成に悪影響が出る可能性があります。
元請けから遠い案件になるほど、単純作業の割合が高くなりやすく、要件定義や設計などの上流工程に関わるチャンスも限られてしまうでしょう。
また、間に複数の企業が入っていると中抜きが発生しやすく、自分の働きに見合った報酬が得られないこともあります。
3次請けや4次請けの案件がすべて悪いわけではありません。
しかし、そうした立場の仕事ばかりが続くと、経験が偏り市場価値を上げにくくなる点には注意が必要です。
4.長時間労働が常態化している
長時間労働が常態化している職場では、心身への負担だけでなく、キャリア形成にも影響が出ることがあります。
残業が当たり前に発生し、場合によっては休日出勤や業務の持ち帰りを求められるケースもあるでしょう。
そうした状況が続くと、プライベートの時間が削られ、十分な休息やリフレッシュができなくなります。
加えて、長時間働いても残業代がきちんと支払われず、エンジニアが搾取されてしまう企業もあります。
さらに、日々の業務に追われることで、技術の習得や自己研鑽の時間も取れなくなり、将来的な働き方の選択肢が狭まってしまうおそれも。
健全なキャリアを築くうえで、働き方を確認しておくことは欠かせません。
5.管理体制が整っていない
管理体制が整っていない職場では、プロジェクトの進行が常に不安定になりやすく、現場のエンジニアに過度な負担がかかることがあります。
場当たり的な判断で無理なスケジュールが組まれたり、上司やマネージャーが現場の状況を十分に把握していないまま進行するケースも少なくありません。
特に客先常駐の案件では、マネジメントの目が届きにくく、指示系統が不明確なまま作業を続ける状況になりやすいです。
そのような環境では、情報共有や判断が遅れ、トラブルが発生しやすくなります。
問題が起きるたびに責任を押しつけられるような状況が続けば、精神的にも追い込まれてしまうおそれがあります。
円滑なプロジェクト運営には、現場と管理側の連携が欠かせません。
6.ハラスメントが横行している
ハラスメントが横行している職場では、業務以外のストレスが増えやすく、安心して働き続けることが難しくなります。
例えば、パワハラやセクハラが日常的に行われているにもかかわらず、周囲が見て見ぬふりをするような環境では、被害を受けても声を上げづらいです。
上司からの圧力によって無理な業務を引き受けざるを得なかったり、クライアントの理不尽な要求がそのまま社員に押しつけられるケースも少なくありません。
そうした状況が続けば、心身に大きな負荷がかかり、働く意欲も削られてしまいます。
ハラスメントの相談窓口が形だけで機能していない企業もあるため、制度の有無だけでなく、実際に使える環境かどうかも確認しておくことが大切です。
7.教育体制が整っていない
教育体制が整っていない企業では、入社後の成長が本人の自己努力に大きく依存することになり、スキルアップやキャリア形成が難航するおそれがあります。
研修やOJTが名ばかりで実務に活かせる内容になっていない場合、現場では属人的な指導に頼ることになります。
そうなると、知識の偏りや曖昧な理解のまま作業を進める状況に陥りやすいです。
さらに、社員の成長を支援する制度や学習用の予算が確保されていなければ、新しい技術を学ぶ機会も限られてしまいます。
教育担当が明確に決まっておらず、質問できる相手がいない環境では、分からないことを解決できず、トラブルの原因になることもあります。
安心してスキルを磨けるかどうかは、長期的に働くうえで欠かせない要素です。
8.福利厚生が充実していない
福利厚生が充実していない企業では、働きやすさや将来の安心感に欠け、長く働き続けることが難しいです。
中には、社会保険以外の福利厚生がほとんど整備されておらず、有給休暇が取得しにくかったり、取得率が極端に低い職場もあります。
また、産休や育休といった制度があっても、利用しにくい雰囲気や前例の少なさから使えない状態にあることも考えられるでしょう。
このような環境では、働きにくさから離職者が増えやすく、結果的に一人当たりの負担がさらに重くなる悪循環に陥るリスクもあります。
社員を大切にする意識が企業側にない場合、待遇の改善も見込めず、将来的な安心を得るのは難しいといえます。
9.離職率が高すぎる
継続して働ける環境かどうかは、転職先を選ぶうえで見逃せない判断材料の一つです。
離職率が極端に高い企業は、職場環境やマネジメントに何らかの問題を抱えている可能性があるため、入社前に確認しておくことが重要です。
短期間で辞める社員が多い場合、残ったメンバーに業務が偏りやすく、負担の集中によってさらに離職が増えるという悪循環に陥りやすい状況が想定されます。
そのような企業では、適切な評価がされていなかったり、スキルや努力に見合った待遇が得られないなど、様々な課題が放置されていることも考えられます。
業界全体の平均と比較して明らかに離職率が高い場合は、表面的な情報にとらわれず、なぜ人が定着しないのかを慎重に見極めましょう。
10.募集要項に具体性がない
募集要項に具体性がない企業は、実際に入社してから想定外の業務や条件を突きつけられるリスクがあるため注意が必要です。
求人票の内容が曖昧で、仕事内容や配属先が詳しく書かれていない場合、入社後に自分の希望とは違う職種や環境に配属される可能性もあります。
また「未経験歓迎」「研修充実」などの抽象的な表現が多く、給与や勤務時間に幅がある場合は、実際の労働条件と異なるケースも少なくありません。
こうした企業では、入社後のギャップからモチベーションを失ったり、早期離職につながることもあります。
募集要項の記載内容に不明点が多い場合は、面接や選考過程でしっかりと確認しましょう。
【業態別】入ってはいけないIT企業の特徴
IT企業のなかでも、自社開発、受託開発、SESなどの業態によって特徴は異なります。
そのため、自分に合った企業を見極めるにはそれぞれの特徴を知っておくことが必要です。
ここからは業態ごとに分けて、入ってはいけない企業の特徴と注意すべきポイントを紹介します。
転職で後悔しないためにも、それぞれの違いを押さえておきましょう。
SIer企業
SIerは、クライアントの要望に応じてシステムの設計から開発、保守までを請け負う受託開発企業を指します。
ただし、元請けに近いポジションであれば上流工程に関われる機会もありますが、下請け構造の末端に位置する企業では注意が必要です。
下流工程だけを担当する環境では、決まった後の作業をひたすら繰り返すだけになりやすく、スキルの幅が広がらず成長する機会が限られることも珍しくありません。
元請けからの急な仕様変更や納期圧力がそのまま現場に降りてくるケースもあります。
結果的に、働く側に大きな負担がかかる場面も少なくありません。
また、受託開発だけでなく、自社サービスを持っているかどうかも、その企業の将来性や柔軟性を見極める材料になります。
自社サービスが継続して利用されている企業は、利益も安定しており、経営自体が揺らぎにくいといえます。
SES企業
SES企業は、エンジニアをクライアント先に常駐させて技術支援を行う契約形態の企業であり、働く環境は配属先によって大きく左右される特徴があります。
特に管理体制が不十分なSES企業では、現場の状況を把握しておらず、長時間労働や不適切な業務内容に気づかないまま放置されるケースもあるでしょう。
また、契約内容が曖昧だったり、業務の内容や就業時間が頻繁に変更されるような企業は、注意が必要です。
長期的に活躍できるエンジニアを目指すうえでは、契約の透明性やサポート体制の有無を事前に確認しておくことが大切です。
避けるべきSES企業に関しては以下の記事でも詳しく解説しているため、気になる方は合わせてご覧ください。
合わせて読みたい
自社開発企業
自社開発企業は自社サービスやプロダクトの企画・開発・運用までを一貫して行う企業ですが、すべての企業が安定しているとは限りません。
特に製品の売上が不安定な企業では、経営基盤そのものが脆弱である可能性が高く、将来性にも不安が残るでしょう。
市場での競争力が弱い企業は、品質管理やプロジェクト管理も後回しにされやすく、エンジニアの業務負荷が過剰になるケースも見受けられます。
自社製品が一つしかない、あるいはごく限られた分野のサービスに特化している場合、技術力は一定レベルまで磨けるものの、他社で通用しにくいスキルに偏ることもあります。
将来のキャリアを見据えるなら、サービスの数や事業の安定性も判断材料になるでしょう。
入ってはいけないIT企業を見極める方法
入ってはいけないIT企業を避けるためには、いかに正確・詳細な情報を集められるかが重要です。
勢いやイメージだけで判断してしまうと、入社後にギャップを感じて後悔するリスクも高まるでしょう。
ここからは、具体的に企業を見極める方法を紹介します。
企業のHPや四季報をチェックする
企業選びにおいて、公式サイトや四季報を確認することは、信頼性の高い情報を得るうえでの基本です。
売上の推移や取引先の規模からは、経営の安定性や将来性をある程度見極めることができ、数値が極端に変動している企業はリスクが潜んでいる可能性もあります。
特に、複数年の売上や利益を比較してみると、一時的な急成長や急落の背景に無理な事業運営がある場合も考えられるため、数字の流れを見ることが大切です。
また、社長メッセージやIR情報からは、その企業がどの方向に向かっているのか、働き方や価値観についての方針も読み取れるでしょう。
これらの情報は、求人票だけでは見えない企業の本質を知るうえで役立ちます。
入社前の判断材料の1つとして、数字と企業のスタンスの両方に目を通しておくことが重要です。
社員の口コミを見る
社員の口コミを確認することで、求人情報だけでは見えてこない職場の実態や雰囲気を把握する手がかりになります。
口コミサイトを活用すれば、実際に働いている人の声から、社内の人間関係や業務量、マネジメントの傾向など、細かな部分まで読み取ることができるでしょう。
ただし、ポジティブな評価だけでなく、離職理由や不満といったネガティブな意見にも目を通すことが大切です。
一時期の意見だけに偏らないよう、複数年にわたる口コミを比較することで、会社の体制が改善されているかどうかの傾向も見えます。
また、口コミ自体がほとんどない企業は、意図的に情報発信を避けていたり、何らかの事情で情報が出にくい環境である可能性も否定できません。
あくまで口コミは参考程度に扱いつつ、他の情報源とあわせて全体像を判断しましょう。
働いている人から話を聞く
企業の実態をより深く理解するには、可能な限り現役社員やOB・OGなど、その職場で実際に働いた経験を持つ人から話を聞くことが有効です。
面接や求人票では見えにくい、職場の雰囲気や上司の人柄、業務の進め方などについてリアルな情報を得られることが多く、入社後のイメージも描きやすいです。
実際に話を聞けば、自分の希望と現場の状況にどの程度ギャップがあるかを明確に把握できます。
また、社内での評価のされ方やキャリアパスの実態なども知ることができ、入社後のミスマッチの回避につながります。
時間に余裕がある場合は、リファラル採用などの機会を活用して接点を持つことも検討しましょう。
直接の声から得られる情報は、口コミだけでは分からない内部事情を知る貴重なチャンスです。
インターンシップに参加する
社内の空気感や実際の働き方を肌で体感できるのが、インターンシップの大きな強みです。
短期間でも現場の雰囲気に触れることで、公式な説明会では伝わりにくい人間関係やチームの温度感を知るきっかけになります。
先輩社員との交流を通じて、仕事の進め方や課題、評価のされ方なども直接聞ける機会もあるため、自分にとって無理のない労働環境かどうかも判断しやすくなるでしょう。
また、インターン終了後に連絡をくれる企業や、選考につながるフォローがあるかどうかも、自社の人材に対する姿勢を見極める材料になります。
就職や転職を成功させるには、外から見た情報だけでなく、実際の現場に触れることで得られる感覚も重視しましょう。
面接で確認する
面接は企業の実態を直接確認できる貴重な機会であり、待遇だけでなく働き方や評価体制についても積極的に質問することが重要です。
配属先や担当業務の詳細、評価制度の内容や昇給の実績などについて質問した際に、回答が曖昧だったり明確な根拠が示されない場合は、入社後のギャップが生まれやすいです。
例えば「入社後に決まります」「状況によります」などの言葉が繰り返される場合は、注意しましょう。
また、面接官の態度や言葉遣い、やりとりの雰囲気からも、その企業の社風や人間関係の傾向をある程度見極めることができます。
面接を一方的に評価される場と捉えるのではなく、自分が安心して働ける環境かどうかを確かめる場として活用しましょう。
IT系に強いエージェントを利用する
IT業界に特化した転職エージェントを活用することで、一般的な求人情報だけでは得られない企業の内情や職場環境に関する具体的な情報を知れます。
IT業界動向に精通した担当者であれば、自分のスキルや希望条件に合った企業を的確に選び、効率よく候補を絞り込むことが可能です。
また、過去にその企業へ転職した人の体験談や、選考時に重視されるポイントなども教えてもらえるため、事前にしっかりと対策を立てるうえでも役立ちます。
さらに、エージェント経由でしか紹介されない非公開求人にアクセスできることもあり、自力では見つからない優良企業に出会える可能性が広がるのも魅力の一つです。
不安な点や疑問があれば相談しながら進められるため、転職活動をより安心して進めたい方にとって心強いサポートになるでしょう。
入ってはいけないIT企業に入らないためにできること
入ってはいけないIT企業を避けるためには、企業側の情報を見極めるだけでなく、自分自身の準備を整えることも欠かせません。
- スキルを磨いておく
- 情報収集を欠かさない
- キャリアプランや希望条件を明確にする
実務に役立つ資格を取得する自己分析や情報収集を行い、信頼できるサポートを得ながら進めていくことで、理想とかけ離れた環境に飛び込んでしまうことを避けられます。
以下の記事も参考にすることで、ホワイト企業に出会うための視点がさらに広がります。
合わせて読みたい
スキルを磨いておく
IT業界で希望に合った企業へ転職するためには、事前に自分のスキルを磨いておくことが重要です。
実務で通用するスキルを持っているほど、企業側から評価されやすく、より条件の良いポジションで採用される可能性が高まります。
単純な作業にとどまらず、新しい技術やフレームワークの習得にも意識的に取り組むことで、技術的な幅が広がり、選考時の説得力にもつながるでしょう。
また、自分の得意領域を明確にしておくことで、企業選びの軸がブレにくくなり、ミスマッチを避けやすくなります。
スキルや実績はポートフォリオやGitHubなどにまとめておくと、応募時のアピール材料に活用できます。
情報収集を欠かさない
入ってはいけない企業を見抜く力を養うためには、日頃から幅広く情報収集を行う姿勢が欠かせません。
企業の公式サイトだけでは実態が分からないことも多く、実際に現場で働いている人の声や、転職経験者の体験談などに触れることで、働くイメージが持ちやすくなります。
また、エンジニア向けの勉強会に参加することで、業界のトレンドや他社の開発体制なども把握でき、知識の習得とネットワーク形成の両面で効果があります。
情報の更新を怠ると、実際の現場とのギャップに気づけず、企業選びの失敗につながりやすいです。
だからこそ、日頃から関心を持って最新の動きを追いかけることが重要です。
キャリアプランや希望条件を明確にする
転職活動を進める前に、自分がどのようなエンジニアになりたいのかを明確にしておくことは、企業選びの精度を高めるうえでは重要です。
将来目指すポジションやスキルの方向性を具体化しておくことで、必要となる案件の種類や開発フェーズも自然と見えてきます。
例えば、要件定義や設計に関わりたいのか、最先端の技術に触れたいのかによって、希望すべき企業の特徴や現場の体制も異なるでしょう。
こうした視点を持たずに漠然と転職を進めると、入社後にギャップを感じたり、キャリアが停滞するリスクも高くなります。
希望条件を言語化しておくことで、自分に合う企業と出会いやすくなり、納得のいく転職につながります。
実務に役立つ資格を取得する
実務に活かせる資格を取得しておくことは、自分のスキルを客観的に証明する手段として、転職活動におけるアピール材料にもなります。
例えば、基本情報技術者や応用情報技術者、AWS認定資格などは、多くの企業で評価の対象となります。
自分の得意分野やキャリアの方向性に合わせて選ぶことで、学習内容そのものが実務にも直結するでしょう。
また、企業によっては特定の資格を保有している人材に対して、年収面やポジションで優遇措置を設けている場合もあり、保有資格の有無が選考結果に影響することもあります。
資格を持っていることで応募できる求人の幅が広がる点も大きなメリットです。
監修者コメント
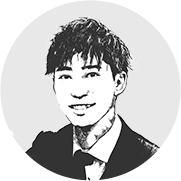
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
“企業を選ぶ前に、自分を整える”という視点がカギ
企業選びに失敗する人の中には、情報不足よりも「自分の働き方の優先順位を整理できていなかった」ことに後から気づくケースが多いです。
例えば、厚生労働省の調査では、在宅勤務における「コミュニケーション不足」がメンタル不調の要因とされています。
また、環境と相性が悪い場合はそれだけで離職リスクが高まると報告されています。
実際、リモートOKの企業に転職しても「レビュー文化がなく相談相手がいなかった…」という理由で、数ヶ月で辞めてしまうエンジニアも少なくありません。
他にも「最新技術やチームレビューで成長したい」と考えていた人が、単独運用案件に配属されてギャップを感じる例もあります。
こうしたミスマッチを防ぐには「何にモチベーションを感じるか」「どんな環境で力を発揮できるか」といった自分の“軸”を事前に言語化しておくことが重要です。
その準備が整えば、求人票や面接で確認するべきポイントが自然と明確になり、企業との相性を実感レベルで判断できるようになります。
他人の条件ではなく、自分にとって理想の働き方に近づけるようになります。
参考:厚生労働省「テレワークの労務管理等に関する実態 調査【概要版】」
まとめ
入ってはいけないIT企業に入ると、スキルが伸びずキャリアが停滞したり、過重労働で心身に不調をきたすなど、将来に大きな悪影響を与えるリスクがあります。
そうした企業には、給与水準が不自然に低かったり、教育体制が整っていない、残業が常態化しているなど、共通する特徴が見られます。
転職で失敗しないためには、求人情報や口コミなどの一部の内容をうのみにせず、自分で情報を集める姿勢が必要です。
また、実務に活かせるスキルを磨いておけば、自分の市場価値を高めたうえで、より良い条件の企業を選びやすくなります。
私たちESESもSES事業を展開していますが、先ほど紹介したように、SESという働き方の中にも「避けるべき企業」があるのも事実です。
その中でESESは、エンジニアが納得感を持って働ける環境づくりを大切にしており、案件選択制度を導入しています。
また、スキルや成果を適切に評価する単価評価制度や高還元率(2025年3月現在、77%)の報酬体系など、やりがいと収入の両立を実現できる仕組みも整えています。
キャリアアップを目指すエンジニアが、無理なく一歩ずつ前進していけるようサポートすることが、私たちの役割です。
選択肢の一つとして、私たちと一緒に働いてみませんか?

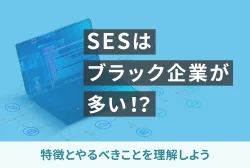



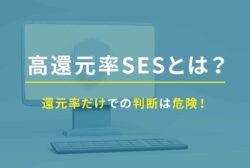
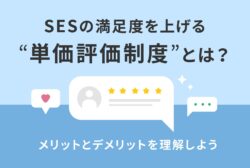
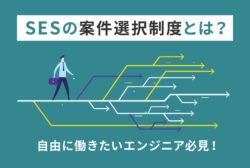
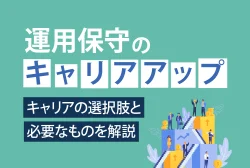

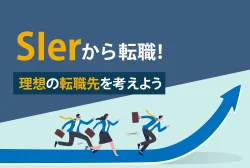
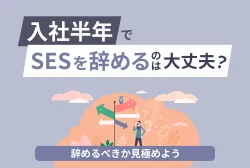
監修者コメント
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
プロフィールを見る
構造に注目すれば、“入ってはいけない理由”が見えてくる
「入ってはいけない企業」の特徴は、単に待遇が悪いだけでなく、抜け出しにくい構造そのものにあります。
例えば、客先常駐で3次請け・4次請けが当たり前になっている企業では、そもそも自社に営業力や交渉力がなく、エンジニアが自分で案件を選ぶ余地がありません。
その結果、配属先は毎回違い、技術の蓄積もされず、スキルも給与も上がらないまま年数だけが経過していく。
そして「人が定着しないから育成に投資できない」「育成されないからスキルが上がらず評価も低い」という悪循環が組織全体に染みついていることもあります。
「なぜその状態なのか」
「改善される仕組みはあるのか」
目の前の条件ではなく、このような視点を持つことで、見えなかった危険信号に気づけるようになります。
3年後の自分が納得できる環境かどうか、構造からも見極めることが重要です。