インフラエンジニアは楽すぎる?仕事内容や求められるスキルを解説

目次
インフラエンジニアは「楽すぎる仕事」として語られることがあります。
確かに、トラブルがなければ比較的落ち着いて業務に取り組むことができ、他の職種に比べて負荷が少ないと感じる瞬間もあります。
実際にはインフラが止まればサービス全体に影響が及ぶため、見えにくいところでプレッシャーのかかる場面も多く「楽すぎる」とは一概には言い切れません。
本記事では、なぜインフラエンジニアが「楽すぎる」と言われるのか、その背景や実際の仕事内容、求められるスキルについて解説します。
「楽すぎる」と言われるインフラエンジニアの仕事内容
インフラエンジニアは、サーバーやネットワーク、データベースなどのITインフラを扱う職種とされています。
これらインフラは、すべてのITサービスの基盤であり、止まると業務に大きな影響を与えかねません。
そのため、インフラエンジニアは裏方ながらも重要な役割を担う存在として、多くの現場で求められています。
業務内容は、大きく分けて設計・構築・運用保守の3つに分類されます。
- 設計:クライアントの課題や要望をヒアリングし、それをもとに最適なインフラ環境を企画
- 構築:設計書をもとに実際の環境を準備し、サーバーやネットワークを動かせる状態に整える
- 運用保守:インフラが24時間365日安定して稼働するように、監視やトラブル対応にあたる
ネットワークに特化したネットワークエンジニアや、サーバー専門のサーバーエンジニアなど、分野に応じて役割が分かれるケースもあります。
近年では、企業のDX推進に不可欠な人材としても注目されており、ビジネス全体を支える存在です。
インフラエンジニアが「楽すぎる」と言われる5つの理由
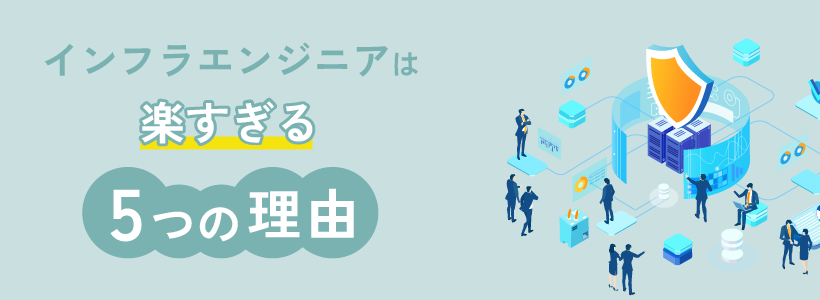
インフラエンジニアは「楽すぎる」と言われることがあります。
ただし、インフラエンジニアにも大変さはあるため、こうした印象だけで「楽すぎる」と断言してしまうのは早計かもしれません。
ここでは、なぜインフラエンジニアが「楽すぎる」と言われるのか、その5つの理由を解説します。
- 作業が自動化・効率化されている
- 柔軟にスケジュール管理できる
- プレッシャーがかかりにくい
- 未経験でも挑戦しやすい
- 多様なキャリアパスを実現できる
1.作業が自動化・効率化されている
近年のインフラ運用では、クラウド環境の普及によって従来のような物理サーバーの保守作業が少なくなっています。
ハードウェアの設置や定期的な機器交換といった作業が不要になり、管理の負担が軽減されてきました。
また、インフラ運用に関わる様々な業務は、ツールの活用によって自動化が進んでいます。
例えば、リソースのスケーリングや監視、バックアップなどはツールに任せることができ、人的な対応は減少傾向にあります。
障害が発生した際も、自動でフェイルオーバーが実行される仕組みが導入されていることも珍しくありません。
こうした自動化を前提とした運用環境では、突発的なトラブル対応の回数も少なく、日々の業務を安定して行える傾向があります。
その結果、インフラエンジニアの働き方が以前に比べて落ち着き、楽に見えるともいえるでしょう。
2.柔軟にスケジュール管理できる
インフラエンジニアの業務は、自動化や効率化が進んでいる影響で、突発的なトラブルがなければスケジュールを立てやすくなっています。
特に運用保守では、定型業務が中心となるため、一度慣れてしまえば日々の作業時間を把握しやすくなります。
その結果、計画的に業務を進めやすくなり、時間に追われることも少ないです。
また、多くの企業でテレワークやシフト勤務といった柔軟な働き方が取り入れられ、自宅やリモート拠点から作業することが一般的になりつつあります。
勤務時間についても、決まった時間に出社する必要がない企業も、生活スタイルに合わせて働くこともできるでしょう。
このような環境では、ライフワークバランスを意識してスケジュール調整をしやすく、私生活との両立もしやすくなります。
安定した業務環境と柔軟な勤務体系の組み合わせによって、楽に見られることがあるのです。
3.プレッシャーがかかりにくい
インフラエンジニアは、表に出ることは少なく、裏方としてシステムを支える立場にあります。
開発エンジニアのように厳しい納期に追われる場面は少なく、精神的な負担は比較的軽いと感じることもあるでしょう。
設計や構築といった工程も、基本的にはチーム単位で進行することが多く、一人に過度な責任がかかる状況にはなりにくい傾向があります。
また、運用保守ではマニュアルが整備されているケースが多く、発生するトラブルも手順に従って対応できる範囲であることが一般的です。
重大な障害対応では緊張感が伴うものの、通常時のプレッシャーは低めといえるでしょう。
安定した体制の中で働けることは、長期的に働きやすい職場環境につながります。
精神的にゆとりを持てるという点も「楽すぎ」と言われる背景の一つです。
4.未経験でも挑戦しやすい
インフラエンジニアは、IT業界の中でも未経験から挑戦しやすい職種です。
実際に、他のエンジニア職と比べても未経験可の求人が多く、キャリアの入り口として選ばれることが多い傾向にあります。
その背景には、業務の多くがマニュアル化されているという特徴があります。
はじめは監視や保守といった定型作業を任されることが多いため、複雑な判断や高度な技術をいきなり求められることは少ないです。
OJTや研修制度が整っている企業も多く、現場で実務をこなしながら少しずつ知識を身につけていける環境です。
システムの構成や運用の流れを理解する経験が積めるため、成長の土台を築きやすいともいえます。
5.多様なキャリアパスを実現できる
インフラエンジニアは、基礎的なITスキルを幅広く身につけられる職種であり、その後のキャリアパスが多様という点でも注目されています。
一定の経験を積んだ後は、ネットワークやクラウドといった特定の分野に専門性を深めていくことが可能です。
設計や構築のフェーズを多く経験する中で、技術の幅と深さが自然と広がっていくでしょう。
また、技術力に加えて、プロジェクトの進行管理やチーム運営に関わる機会も増えていきます。
その結果、マネジメント寄りのポジションに進むケースも多く、リーダー職や管理職の道も拓かれやすいです。
さらに、一定のスキルと経験を持つことで、フリーランスとして独立する人や、企業内の情報システム部門で社内SEとして活躍する人もいます。
「楽すぎる」とは言えないインフラエンジニアの大変さ
インフラエンジニアは「楽すぎる」と言われる一方で、実際に働いてみると想像以上にハードだと感じる場面もあります。
見えにくい部分で責任や緊張感が伴うこともあり、のんびりと安定して働ける職種とは一概に言い切れません。
ここでは「楽すぎる」だけではない、インフラエンジニアの大変さを解説します。
インフラエンジニアのリアルな一面をもっと知りたい方は、こちらもチェックしてみてください。
合わせて読みたい
迅速な対応が求められる
インフラエンジニアは、システム障害やトラブルが発生した際に、迅速で正確な対応を求められます。
障害対応は、時間との勝負になるケースもあり、対応の遅れが事業全体に大きな影響を与えることもあります。
近年は自動化や効率化が進んでいるものの、すべての問題がツールで解決できるわけではありません。
トラブルの内容や規模によっては、一刻を争う場面に直面することも十分に考えられます。
そのため、原因を素早く特定し、影響範囲を見極めながら復旧を進める力が欠かせません。
深夜や休日に緊急対応が発生するケースもゼロではなく、オンコール体制を敷いている現場もあります。
こうした状況に対応するには、チーム内での連携や情報共有も重要であり、個人プレーだけでは乗り越えられないことも多いです。
落ち着いて見える日常業務の裏では、いざという時に備えた高いスキルと責任感が求められます。
生活リズムが不安定になりやすい
インフラエンジニアは、システムを24時間365日止めずに稼働させる役割を担っているため、夜勤やシフト勤務が発生する現場も多いです。
運用保守の担当者は、夜間や休日でも障害が発生すれば対応が必要になることがあり、生活リズムを保ちにくくなりがちです。
不規則な勤務によって、睡眠時間がばらついたり、日中に十分な休息がとれない状況に陥ることもあります。
慣れるまでは体調を崩しやすく、疲労が慢性的にたまりやすい点も無視できません。
こうした働き方に順応するためには、日頃からの健康管理や睡眠の質を意識する必要があります。
業務が効率化されていても、このような生活面での負担は避けられず、インフラエンジニアの見えにくい大変さの一つといえるでしょう。
新しい技術を学び続ける必要がある
IT業界は技術の進化が早く、インフラエンジニアもその変化に対応し続けることが求められます。
ここ数年で、クラウドサービスやIaC、コンテナ技術などが急速に普及し、従来の物理サーバー運用の知識だけでは不十分になってきました。
オンプレミスの経験があっても、クラウドネイティブな構成や最新の自動化ツールに対応できなければ、業務の幅が狭まってしまう可能性があります。
日常業務だけで満足せず、新しい技術に対して学ぶ姿勢を持ち続けることが重要です。
実際に、資格の取得を目指したり、社内外の勉強会に参加して知識を深めるエンジニアも少なくありません。
継続的な学習が求められる点は、インフラエンジニアが働くうえでの見落としやすい大変さの一つといえるでしょう。
「楽すぎ」と言われるインフラエンジニアに求められるスキル
インフラエンジニアは「楽すぎる」と言われがちですが、実際には幅広いスキルと強い責任感が求められる仕事です。
日々の運用が安定して見えるのは、障害を未然に防ぐ設計や、自動化の仕組みを整えてきた結果ともいえるでしょう。
努力を積み重ねたうえで、初めて「安定している」「余裕がある」と感じられる状態が生まれるといえます。
ITインフラに関するスキル
インフラエンジニアが働くうえで、サーバーやネットワークといったITインフラに関する基本的な知識は欠かせません。
OSの構成やネットワーク機器の設定といった物理・論理の理解があることで、障害発生時の原因特定や復旧もスムーズに進められるでしょう。
加えて、現在の現場ではクラウドサービスの導入が一般的になっており、AWSやAzureなどの運用経験があると、対応できる業務の幅が広がります。
クラウドにおけるリソース管理やアクセス制御の仕組みを理解しておくことは、今後のキャリアにとっても有利に働きます。
また、セキュリティやバックアップの仕組みを正しく設計・運用できるかどうかも、安定したサービス提供において重要な視点です。
日々の業務に直結するこれらのスキルを身につけることが、インフラエンジニアとして信頼される第一歩になるでしょう。
プログラミングスキル
インフラエンジニアは、必ずしも本格的なプログラマーである必要はありません。
ただ、基本的なプログラミングやスクリプトの知識があると業務効率が大きく変わります。
現場でよく使われる言語の例は以下の通りです。
- シェルスクリプト:Linux環境での操作自動化や定期処理に使用される
- PowerShell:Windows環境での管理業務や構成変更に適している
- Python:汎用性が高くツール開発やログ解析など幅広い場面で活用される
これらを使いこなせるようになると、トラブル対応や構成変更のスピードも向上し、ミスの削減にもつながるでしょう。
多くの現場では、チーム内に専任のプログラマーがいる場合もありますが、自分自身でコードを書けるようになると、差別化にもつながります。
結果的に、技術の幅が広がるだけでなく、将来的なキャリアの選択肢も広げられます。
コミュニケーションスキル
インフラエンジニアは、技術だけでなく人との連携も重要になる職種です。
日々の業務では、社内の開発チームや運用担当者、さらには外部ベンダーやクライアントとやり取りする機会が多いです。
特に障害対応時には、状況を正確に把握し、関係者へ適切な報告・連絡・相談を行う力が問われる場面もあるでしょう。
相手に不安を与えず、要点を整理して伝える姿勢が、トラブルの早期解決や関係性の維持に直結します。
また、調整業務では相手の事情や立場に配慮しながら折り合いをつける必要があるため、単なる伝達能力にとどまらず、共感や配慮のスキルも求められます。
こうした対応力を積み重ねることは、信頼を得る土台となり、将来的なリーダー職やマネジメント職への道を広げる要素です。
マネジメントスキル
インフラエンジニアは、設計から構築、運用までの各フェーズに関わるため、複数の案件やタスクを並行して進める場面が多いです。
限られた時間の中で優先順位を見極め、計画的に業務を進めていく力が求められます。
社内メンバーや外部ベンダーとの連携も頻繁に発生するため、コミュニケーション能力に加えて、進捗管理やリソース調整といったマネジメントスキルも重要です。
一人で完結する業務ばかりではないため、チームの動きを把握しながら全体の最適化を意識する姿勢が求められます。
将来的にプロジェクトリーダーやマネージャーを目指す場合には、技術スキルだけでなく、組織を動かす力を養っておくことが大切です。
個人で成果を出す段階から、チーム全体の成果をつくる立場へと進むためには、マネジメントの経験が大きな武器になります。
早い段階から意識して取り組んでおくことで、キャリアの選択肢も広がっていくでしょう。
監修者コメント
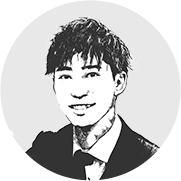
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
技術力だけでは語れない、もう一段上のインフラスキル
インフラエンジニアというと、Linuxの知識やクラウド構築、スクリプトでの自動化といった技術スキルに注目されがちです。
しかし、それだけでは安定運用を実現することはできません。
例えば、障害が発生したときには、構成図を頭に思い浮かべながら「どの機能が止まり、どこに影響するのか」を瞬時に判断する“構成把握力”が求められます。
同時に、監視ログやアラートを読み解く“情報整理力”や、リソース逼迫時に何を優先すべきかを判断する“現場対応力”も不可欠です。
また、プロジェクトが並行する中では、関係者とのスケジュール調整や、作業の優先順位づけといった“運用マネジメント力”も問われる場面があります。
見えないところで起こる問題を先回りして想定し、冷静に対応できる「思考力」や「判断力」もインフラエンジニアには欠かせないスキルなのです。
技術だけでなく、こうした視点も意識しながら経験を積むことで、次のレベルへのステップアップにつながります。
「楽すぎる」と言われるインフラエンジニアについてよくある質問
インフラエンジニアに関心を持つ人の中には、具体的な疑問を抱えるケースがあります。
転職を検討している段階では、現場の実態やキャリアパス、必要なスキルなどが不透明で、不安を感じる人も少なくないでしょう。
そこで、インフラエンジニアの仕事や転職に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1.やりがいはあるの?
「楽そう」と見られることもあるインフラエンジニアですが、やりがいもあります。
目立つ場面は少ないものの、インフラエンジニアはシステム全体を支える基盤に携わる大切なポジションです。
以下のような点に魅力を感じる方には、向いている職種ともいえます。
- システムの根幹に関わるため、責任感と達成感を得やすい
- 大規模なインフラを扱う機会があり、影響力の大きな業務に携われる
- クライアントとの信頼関係を構築し、長期的に関われる場面もある
- ネットワークやクラウドなど、幅広い技術を身につけることができる
- 安定性の高い領域でキャリアを積み上げやすく、長期的な成長が見込める
インフラという縁の下の力持ちのような役割に価値を見いだせる人にとって、やりがいの多い職種です。
さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
合わせて読みたい
Q2.インフラエンジニアに転職する時のコツは?
インフラエンジニアへの転職を目指す際には、事前の準備や方向性の整理が必須です。
中でも意識しておきたいのが、以下の4つのポイントです。
- 業務で活かせるスキルを身につけておく
- 基礎知識の証明に使えるインフラ関連の資格を取得する
- 自分に合った働き方やキャリアパスを整理し、希望条件を明確にする
- 想定質問や過去の経験を踏まえた面接対策を行う
また、企業選びは焦らず慎重に行いましょう。
スキルレベルや将来のキャリアイメージだけでなく、入社後の研修制度やサポート体制、働きやすさにも注目する必要があります。
転職を成功させるためには、求人票だけで判断せず、多角的に比較・検討する視点が欠かせません。
基本を押さえながら着実に準備を進めれば、納得のいく転職につながります。
詳しく知りたい方は、こちらの記事もチェックしてみてください。
合わせて読みたい
Q3.インフラエンジニアと開発エンジニアで迷ってます……
インフラエンジニアと開発エンジニアのどちらに進むべきか迷う人は少なくありません。
どちらもIT業界に欠かせない職種であり、それぞれ異なる役割や適性があります。
まず、インフラエンジニアに向いている人は、以下のような傾向があります。
- 技術に対して継続して学ぶ姿勢がある
- サーバーやネットワークなど、機械を扱うことに興味がある
- 集中して地道な作業を進められる
一方で、開発エンジニアに向いているのは以下のようなタイプです。
- 勉強し続けるのが苦にならない
- 仕様に沿ってコツコツとコードを書くのが得意
- 環境や要件の変化に柔軟に対応できる
どちらが優れているということではなく、それぞれの特性に応じた仕事が求められています。
自分の性格や興味、働き方のイメージに合ったほうを選ぶことが大切です。
選択に迷った際は、両者の違いを比較しながら整理してみると、進むべき方向が見えてくるかもしれません。
どちらを選んでもキャリアの可能性は広がるため、焦らず判断していきましょう。
合わせて読みたい
まとめ
「インフラエンジニアは楽すぎる」といった声がある一方で、実際には多くのスキルや責任が求められる仕事です。
たしかに自動化やリモートワークの普及により、落ち着いた働き方がしやすい側面もありますが、障害対応や生活リズムの不規則さなど、大変さも少なくありません。
そのため、楽かどうかの感じ方は人によって異なります。
自分がどのような働き方を望むのか、どんなスキルを身につけたいのかを考えながら、進む方向を決めることが大切です。
もし、まだ自分に合う分野がはっきりしていない場合は「まずはSES企業で経験を積む」という選択肢もおすすめできます。
SES(システムエンジニアリングサービス)は、自社の正社員としてクライアント先に常駐し、多様な現場で開発や運用に携わる働き方です。
複数の案件を経験することで、向き不向きを見極めながらスキルを磨けるため、キャリアの方向性も考えやすいです。
弊社ESESもSES企業の一つで、エンジニアが納得感を持って働ける仕組みを作っています。
案件選択制度により、業務内容やスキル領域を自分で選べるほか、単価評価制度・高還元率(2025年3月現在、77%)といった待遇面でも制度を整えています。
働きやすい環境の中で、理想のキャリアや得意分野を見つけていきましょう。




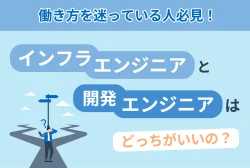


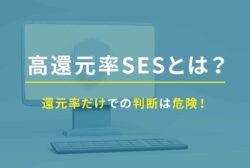
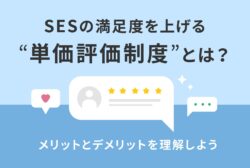
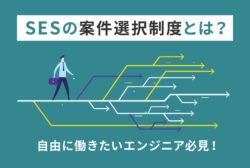

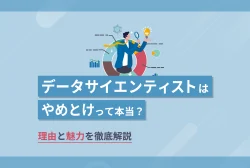
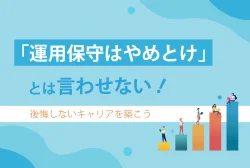
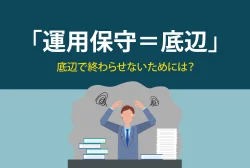
監修者コメント
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
プロフィールを見る
“楽そう”の裏には、設計力と責任がある
インフラエンジニアは「楽そう」「暇そう」と見られることがありますが、それはあくまで“トラブルが起きていない状態”を実現できているからにすぎません。
例えば、CPUやメモリのリソース使用率を定期的に監視し、しきい値を超える前にスケールアウトの判断をする。
ディスク容量のアラートを、自動で通知する設定にしておく。
冗長構成でWebサーバーやDBサーバーを組み、障害が発生しても自動でフェイルオーバーする設計を構築しておく。
これらのような仕組みを日頃から整備・運用し続けることで、目に見えるトラブルが減り「何もしていないように見える」状態が生まれているのです。
TerraformやAnsibleを使った構成自動化もその一例で、作業の安定性を担保しつつ、工数の最適化も実現しています。
インフラが止まれば全サービスが止まる可能性があるため、求められるのは高い責任感と地道な設計力です。
派手さはなくても「何も起きない」を支える技術と覚悟にやりがいを感じられる人こそ、インフラエンジニアに向いているといえます。