クラウドエンジニアにおすすめの資格12選|学習するときのポイントも解説
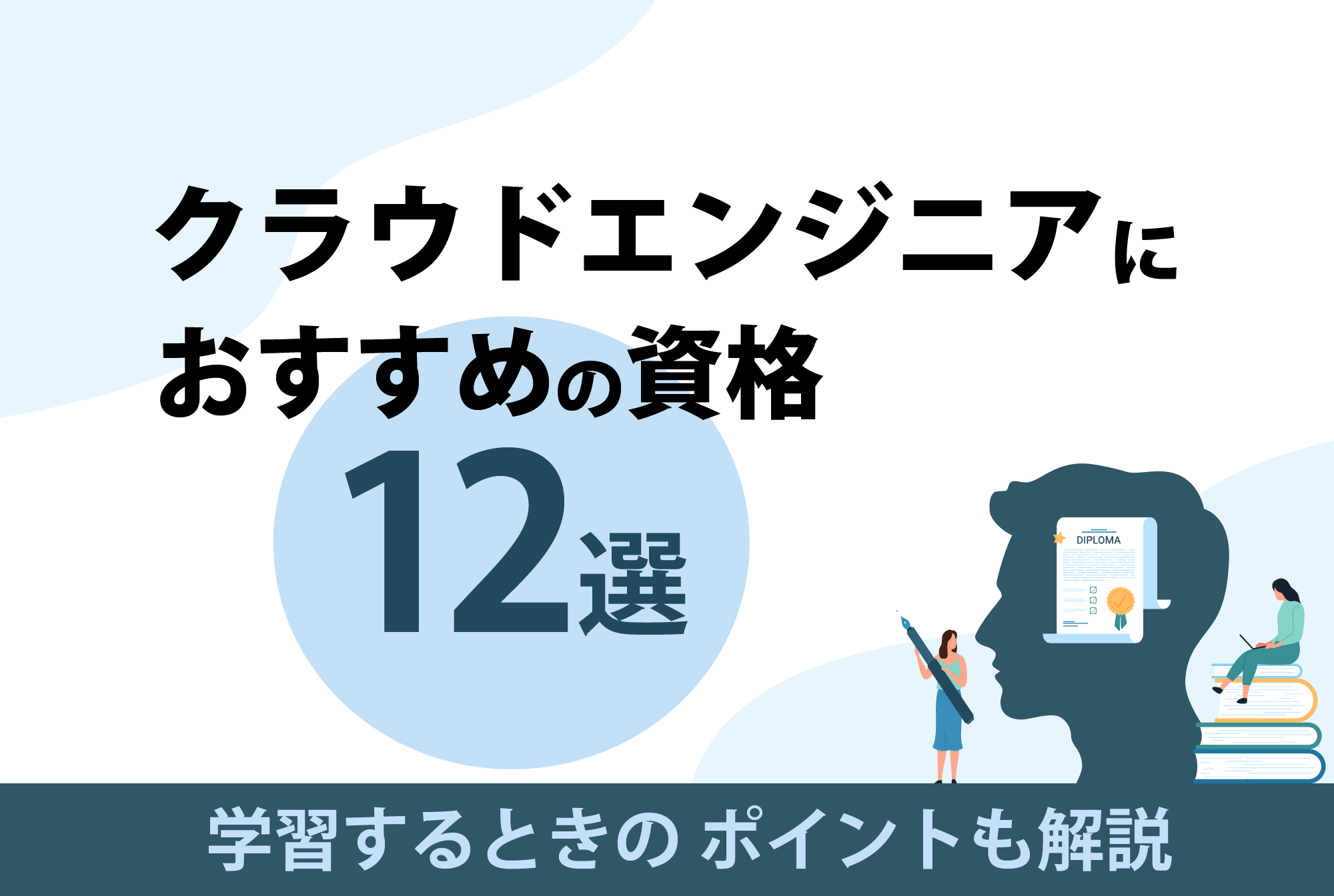
「今より年収を上げたい」
「もっと市場価値を高めたい」
このような思いを抱えているエンジニアも多いでしょう。
クラウドエンジニアは、最適なITインフラを設計し、安定して運用できる環境を支える、需要の高い職種のひとつです。
この分野で確実にスキルアップしていくために欠かせないのが、客観的なスキルの証明になる資格の取得です。
この記事では「なぜクラウドエンジニアに資格が必要なのか?」を解説しながら、キャリアアップや転職にも直結するおすすめ資格12選を紹介します。
今のスキルレベルや目指す方向にあわせて、自分にぴったりの資格を見つけるヒントを得られるはずです。
クラウドエンジニアが資格取得するべき理由
クラウドエンジニアが転職やキャリアアップを目指すなら、資格は強力な武器になります。
その理由は以下の5つです。
- スキルの証明になる
- 実務に即したスキルを得られる
- 市場価値を高められる
- キャリア形成に有利に働く
- 年収アップにつながる
実務に即した内容を学べる資格も多く、業務理解を深めるきっかけにもなるでしょう。
スキルを客観的にアピールすることで、企業やクライアントからの信頼獲得にもつながります。
スキルの証明になる
クラウドエンジニアとして活躍するには、日々の業務に必要な知識や技術を学ぶことが欠かせません。
しかし、ただ勉強しただけでは相手に自分のスキルを伝えるのは、難しい場面もあります。
そこで有効なのが、資格の取得です。
資格は「この分野の知識を体系的に理解している」という客観的な証拠になるからです。
書類選考や面接の際にもアピール材料になり、転職活動を優位に進める後押しとなるでしょう。
実務に即したスキルを得られる
資格試験は実務を想定して構成されており、暗記すればいいような問題ばかりではありません。
設計、構築、運用、セキュリティなどの業務で求められる判断力や理解力が試されるため、学習そのものが実務に直結しやすいです。
その結果、現場での対応力が向上し、課題解決のスピードや提案の質も向上するでしょう。
ただの理論ではなく、実務に役立つ知識を効率よく身につけられる点で、資格取得の価値は高いといえます。
市場価値を高められる
資格には難易度の違いがあり、上位資格を取得していれば、それだけ高い専門性を持っていることの証明になります。
特にクラウド分野は専門性が求められる領域のため、第三者から見て実力を判断しやすい資格は、信頼につながりやすいでしょう。
また、就職や転職の場面では、履歴書や面接でのアピール材料となり、他の応募者との差別化を図れます。
実際に働き始めてからも、希望するプロジェクトへの参画や条件面での優遇にもつながりやすくなります。
キャリア形成に有利に働く
クラウドエンジニアとして「どんなキャリアを築きたいか」が明確でも、その領域の知識やスキルが備わっていなければ、希望する案件に関わることはできません。
現場では即戦力が求められるため、キャリアプランに沿った資格を取得していることは、信頼されやすくなる要素のひとつです。
極めたい分野に関連した資格を取得しておくことで「スキルを持っている人材」として評価される可能性が高まります。
その結果、責任あるポジションや上流工程も任せてもらいやすく、キャリアアップしやすいといえます。
年収アップにつながる
資格を保有していれば、そのレベルに応じたプロジェクトや業務に参画しやすくなり、よりレベルの高い仕事を任される機会も増えます。
業務の難易度が上がるほど、それに見合った報酬が支払われる傾向があるため、収入面での伸びも期待できるでしょう。
企業によっては資格手当を導入している場合もあり、保有資格によって毎月の給与に上乗せされるケースも珍しくありません。
知識を得るだけでなく、それを形にして評価される手段として、資格取得は未来の自分のための投資といえるでしょう。
クラウドエンジニアにおすすめの資格12選
クラウドエンジニアとして資格を取得する際は、ただ有名だからという理由で選ぶのではなく、自分の目的や状況に合ったものを見極めることが大切です。
資格ごとに難易度や学習時間が異なるため、現在のスキルレベルや実務経験に合ったものを選ばなければ、途中で挫折する可能性もあります。
「将来的にどんな案件に関わりたいか」といった視点も重要です。
資格を選ぶときは、以下の条件を考慮しましょう。
- 難易度
- クライアントのニーズ
- トレンド
- 自身のキャリアプラン
時代の流れや業界のトレンドを押さえた資格であれば、今後のニーズに対応しやすくなります。
自身のキャリアプランに沿った資格を選べば、スキルの積み上げが無駄にならず、長期的に見て効率的な成長にもつながるでしょう。
以下、おすすめの資格を紹介します。
AWS認定資格
クラウドエンジニアとしてキャリアを築くうえで、まず検討したいのが「AWS認定資格」です。
AWS(Amazon Web Services)は、世界中で最も広く利用されているクラウドサービスのひとつであり、その信頼性と実績から多くの企業が導入しています。
AWSに関する知識とスキルを証明する認定資格は評価されやすく、企業によっては取得を応募条件にしている場合もあります。
また、AWS認定資格は分野や難易度ごとに細かく分かれているのも、特徴のひとつです。
自身のスキルや将来的に目指すキャリアに応じて段階的に選べるため、効率よく学びながら実務に活かせるでしょう。
信頼性の高い資格であると同時に、実践力を高めるきっかけにもなるため、クラウドエンジニアを志すなら積極的に取得を検討したい資格といえます。
参考:AWS「AWS認定」
Google Cloud認定資格
Google Cloud認定資格は、Googleが提供するクラウドサービス「Google Cloud Platform(GCP)」に関するスキルを証明できる国際資格です。
GCPは、ビジネス分野におけるデータ管理やアプリケーション運用に強みを持ち、AI・機械学習との連携や大規模データ処理にも適しています。
この資格の特徴は、実務を前提に構成された試験内容にあり、知識だけでなく現場での判断力や対応力まで求められる点です。
GCPを導入する企業は年々増えており、将来的な需要の高まりを見越して、早めの取得を視野に入れておきましょう。
参考:Google Cloud「Google Cloud 認定資格」
Microsoft Azure認定資格
AzureはMicrosoftが提供するクラウドプラットフォームです。
以下のように、企業向けに幅広いサービスを展開しています。
- インフラ構築
- アプリケーションの運用
- セキュリティ対策
- データベース管理
実際の業務でもAzureを活用するケースは年々増えており、業務に直結する知識としてその重要性は無視できません。
大手企業や官公庁での導入事例が多いため、Azureに関するスキルを持っていると、対応できる案件の幅も広がるでしょう。
Azureに特化して活躍しているエンジニアは「Azureエンジニア」として業界内で認知されており、スキルがあること自体が市場価値の高さを示す要素にもなります。
Microsoft Azure認定試験について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
合わせて読みたい
参考:Microsoft「Microsoft Azure認定資格」
情報処理安全確保支援士試験
情報処理安全確保支援士試験は、サイバーセキュリティ分野において高い専門性を持つことを証明できる国家資格です。
単に知識を持っているだけでなく、実務での運用能力に加えて、組織内での指導や助言まで担える水準が求められるため、難易度は高めといえるでしょう。
しかし、その分評価も高く、特に近年ではサイバー攻撃への対策が経営レベルで重要視されていることから、企業の関心も強まっています。
- システムの脆弱性への対応
- リスク管理
- インシデント発生時の対応方針
この資格を持っていることで業務の中核を担う役割を果たせる人材として期待され、社内外からの信頼性が上がります。
公的機関や大企業のセキュリティ関連のポジションでは、情報処理安全確保支援士の資格の有無が選考基準のひとつになることもあります。
参考:情報処理推進機構「情報処理安全確保支援士試験」
ネットワークスペシャリスト試験
ネットワークスペシャリスト試験は、大規模なネットワークや、インフラに関わるエンジニアにおすすめの資格です。
ネットワークの設計から構築、運用、保守に至るまで自ら対応できるスキルに加え、他の技術者へ指導や助言を行う立場でも活躍できることを証明できるのが特徴です。
ネットワークの基礎的な知識だけでなく、最新のITサービス動向や技術トレンドまで広くカバーし、高度な専門家としての能力が求められます。
参考:情報処理推進機構「ネットワークスペシャリスト試験」
情報処理技術者試験
情報処理技術者試験は、IT分野における基礎的かつ体系的な知識を証明できる国家資格です。
「基本情報技術者試験」と「応用情報技術者試験」の2つに分かれており、それぞれITエンジニアとしての理解度や応用力を測る内容となっています。
クラウドエンジニアとして長期的に活躍していくことを考えるなら、基本だけでなく応用まで取得しておくことが望ましいです。
資格を持っていることでプロジェクトの中核を担う立場として認識されやすくなり、キャリアアップの足がかりにもなります。
基礎を固めたい初学者から、今後の成長を見据えた中堅エンジニアまで、幅広い層におすすめできる資格です。
参考:情報処理推進機構「情報処理技術者試験」「応用情報技術者試験 」
LinuC
LinuCは、世界中で広く利用されているOS「Linux」に関するスキルを証明できる認定資格です。
Linuxは多くのサーバーやクラウド環境で採用されており、特にインフラやバックエンド領域では使用頻度が高いです。
クラウドエンジニアとして活躍していく上で、欠かせない知識や技術が学べるといえます。
LinuCを取得することで、Linuxに関する実務レベルのスキルを持っていることを客観的に示すことができ、採用担当者やクライアントからの信頼にもつながります。
参考:LPI-Japan「LinuC」
CCNA
CCNA(Cisco Certified Network Associate)は、ネットワーク機器メーカー大手のシスコシステムズ合同会社が提供する認定資格です。
ネットワークの基礎知識を幅広くカバーしており、インフラの土台となる部分を体系的に学ぶことができます。
クラウドエンジニアリングとも密接に関係しており、クラウド上でのネットワーク構成や接続設計を理解するための基礎力を養うには最適な資格といえるでしょう。
クラウド環境の運用やトラブル対応においても、ネットワークの基本が理解できていれば柔軟かつ的確な対応が可能になるため、現場での信頼性も高まります。
参考:Cisco「CCNA」
CompTIA認定
CompTIA認定資格は、IT分野における国際的な標準化団体であるCompTIA(Computing Technology Industry Association)が提供する認定プログラムのひとつです。
CompTIAは世界中の企業や教育機関とパートナーシップを結んでおり、グローバルな影響力と高い信頼性を持つ団体として知られています。
中でもクラウドエンジニアにおすすめなのが、クラウドに関連する「CompTIA Cloud+」です。
特定のベンダーに依存しない汎用的な知識を体系的に学べる点が強みです。
クラウドエンジニアとしての土台をしっかり固めたい人や、将来的に複数のクラウドサービスを扱いたいと考えている方にとって、実用性の高い資格といえます。
参考:CompTIA「CompTIA認定資格」
CCSP認定試験
CCSP(Certified Cloud Security Professional)認定試験は、クラウドセキュリティ分野に特化した国際的な資格です。
高度な専門知識を持つことを証明できる点が特徴です。
クラウド環境の普及に伴い、企業が取り扱うデータ量が増えてシステムも複雑になっているため、セキュリティ対策の重要性も高まっています。
そのため、CCSPのようなクラウドセキュリティに特化した資格を持っているエンジニアは、企業にとって重宝されるでしょう。
試験では以下のような実務で直面するリスクに対して、どのように対応すべきかが問われます。
- データ保護
- アクセス管理
- 脅威の検出
- コンプライアンスなど
クラウドエンジニアとしてセキュリティ領域までカバーできれば、より高度な案件に携わるチャンスも広がるでしょう。
参考:ISC2 Japan「CCSP認定試験」
VMWare認定
VMWare認定資格は、仮想化技術の分野で世界的に高い評価を受けている資格です。
クラウドエンジニアとして仮想化のスキルを持っていることを客観的に示す材料になります。
仮想化はクラウド環境の基盤となる技術のひとつであり、効率的なリソース運用や柔軟なシステム構築を実現するうえで欠かせない要素です。
そのため、クラウドエンジニアとして仮想化の技術力を持っていることは、現場での即戦力として評価されるポイントになります。
VMWare認定は世界共通の資格であり、日本国内だけでなく海外企業や外資系企業との案件でも十分なアピール材料となるでしょう。
クラウドと仮想化の両方を扱えるエンジニアとしての信頼を高めたい方に、特におすすめです。
参考:VMware「VMware認定資格」
Alibaba Cloud認定資格
Alibaba Cloud認定資格は、中国の大手IT企業であるAlibabaが提供するクラウドサービス「Alibaba Cloud」に関する知識と技術力を証明する国際資格です。
この資格では、単なる理論的な知識だけでなく、実際のプロジェクトでの活用経験やサービスへの深い理解が求められます。
Alibaba Cloudは中国をはじめとしたアジア地域で圧倒的なシェアを持っています。
近年では欧米や東南アジアなどでも導入が進んでおり、グローバルな展開を視野に入れたエンジニアにとっては大きな武器となるでしょう。
参考:ピアソンVUE「Alibaba Cloud認定資格」
クラウドエンジニアが資格取得に向けて学習するときのポイント
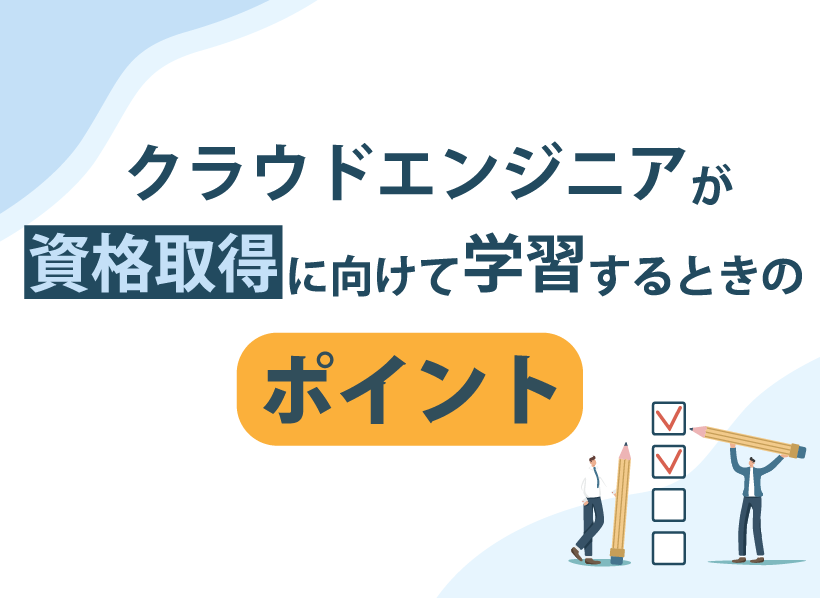
資格取得には、長期的な学習が必要になることが多いため、無理なく継続できる方法で進めることが重要です。
いきなり高難度の資格に挑戦したり、一気に複数の資格を狙うと、途中で挫折してしまうリスクも高くなります。
自分のペースに合わせて学習計画を立て、少しずつステップを踏んでいくことが成功のカギとなります。
特に仕事と両立しながら勉強を進める場合は、効率的に学ぶ工夫や、自分なりのモチベーション維持の方法を見つけておくことも欠かせません。
ここでは、挫折せずに学習を継続するための具体的なポイントを紹介します。
学習計画・目標を立てる
資格取得を目指す際は、ただ「合格する」という目標を掲げるだけでなく、そこに至るまでの道筋を具体的に計画しておくことが重要です。
計画を明確にしておくことで学習スケジュールや進捗の管理がしやすくなり、自分が今どこにいて何をすべきかが分かるようになります。
資格を取った先にどんなキャリアを描きたいのかという長期的な目標も設定しておくと、学習への意義が明確になり、日々の勉強に対する意識も変わります。
結果として、学習の継続につながり、モチベーションの維持にも効果を発揮するはずです。
1つずつ取得を目指す
あれもこれもと手を広げるより、1つの資格に集中して取り組むことが効果的です。
複数の試験範囲を同時に学習すると、知識が混在してしまう恐れがあります。
その結果、学習効率が落ちてしまい、かえって時間がかかるケースも少なくありません。
一方で、1つの資格に絞って学習すれば、内容を深く理解できるうえ、知識も定着しやすいです。
集中して学ぶことで短期間での合格も狙いやすくなり、さらに次の資格に向けたモチベーションも高まりやすくなるでしょう。
優先度の高い資格に絞って学ぶ
限られた時間を有効に使うためにも、優先度の高い資格に絞って学習することが重要です。
資格は合格までに一定の準備期間が必要となるため、何をどの順番で学ぶかを明確にしておくことで、無駄な労力や時間を減らせます。
まずは、自分の現在のスキルセットや業務内容、将来的に目指すキャリアをふまえ「今必要な資格は何か」「取得すればどんなメリットがあるのか」を整理しましょう。
例えば、転職や昇進を見据えているなら、企業の評価が高い認定資格を優先するなど、目的に沿った取捨選択が大切です。
優先度を考えて学習対象を絞ることで、より集中して学ぶことができ、結果として短期間での成果にもつながりやすくなります。
実践演習にも取り組む
クラウドエンジニアとして資格を取得する際は、テキストや動画による座学だけで学習を終えるのではなく、実際に手を動かしてアウトプットすることが不可欠です。
特にクラウド分野は、サービスの構築や操作方法、トラブル対応など「やってみないと身につかない・レベルアップしにくい」部分が多いです。
知識として理解できていても、実際の操作がスムーズにできなければ、実務で活かすことは難しいかもしれません。
だからこそ、模擬環境や無料枠のあるクラウドサービスを活用しながら、自分の手で設定を試してみましょう。
エラーに対応し、動作の仕組みを確かめていくことで、理解が深まります。
実践を重ねることで知識を実務で活かせるようになるため、資格試験の合格だけでなく、業務でも即戦力としての活躍が期待されるでしょう。
モチベーションを維持できる方法で学ぶ
クラウドエンジニアを目指して資格の勉強をするうえで、多くの人が直面するのがモチベーションの維持です。
独学は自分のペースで進められる反面、疑問を解決しづらかったり、学習仲間がいないことで孤独を感じやすくなります。
学び始めは順調でも、徐々に気持ちが薄れてしまい、途中で手が止まってしまうケースも少なくありません。
そのため「一人では続けられそうにない」と感じた時点で、環境を変える選択をするのもおすすめです。
例えば、オンラインスクールやコミュニティに参加すれば、質問ができる環境があり、同じ目標を持つ仲間と刺激を受けながら学習を続けやすくなります。
無理に一人で頑張ろうとせず、自分に合ったモチベーション維持の方法を見つけることが、資格取得への近道といえるでしょう。
監修者コメント
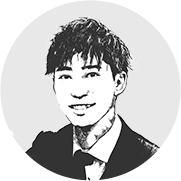
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
資格を活かす人が伸びる
資格取得はゴールではなく、キャリア構築のスタート地点です。
特にクラウド分野は技術の移り変わりが速いため、合格後も継続的に手を動かし、最新のサービスや実務課題に触れ続ける姿勢が重要です。
一度試験に合格したからといって、そこで学習を終えるのではなく、その分野の最新情報をキャッチアップし続けましょう。
そうすることで、自身のスキルを磨き続けられるだけでなく、周囲からも学習意欲が評価されます。
また、学習計画を立てる際は、試験範囲だけでなく「資格取得後にどのようなプロジェクトに関わりたいか」まで逆算して考えると、学びの質が格段に上がります。
学んだ知識を実際にどう活かすか考えることで、モチベーションを維持することができ、自分に足りない知識が明確になるのです。
知識のインプットと実践のアウトプット、この両輪を回し続けることで、本当に価値あるスキルへと育っていきます。
ただ資格を取得するだけでなく、それをどう活かすかを考えてみてください。
まとめ
本記事では、クラウドエンジニアが資格を取得すべき理由や、おすすめの資格を12個紹介しました。
資格にはスキルの証明から年収アップまで、多くのメリットがあります。
資格ごとに難易度や分野が異なるため、自分の現在のスキルや今後のキャリアプランをふまえて、最適なものを選ぶことが大切です。
受験する資格が決まったら、学習計画を立て、モチベーションを保てる環境を整えて、確実に合格を目指していきましょう。
「資格取得で終わらせず、しっかり実務経験を積みたい」と考えている方は、SES企業への就職も検討してみてください。
SES(システムエンジニアリングサービス)は、SES企業に所属しながら外部のプロジェクトに参画する働き方です。
弊社ESESは、無理なアサインをせず、エンジニア一人ひとりのキャリアプランや希望に沿って、参画案件を選べる制度を導入しています。
資格の勉強をしているエンジニアには、その内容に合った技術や工程に関われる案件を紹介することも可能です。
「資格を取って終わり」ではなく、実務を通じて知識を深めたい方にとって、理想的な環境といえます。
ESESでは、クラウドエンジニアとして「なりたい自分」を実現できるサポート体制が整っています。
あなたのキャリアに合わせて、働きやすい環境で経験を積みながら、次のステップを踏み出してみませんか?
SESエンジニアに興味がある方は、ぜひ募集要項もご覧ください。




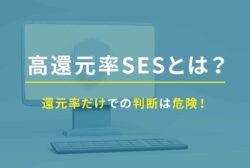
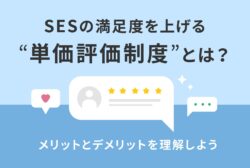
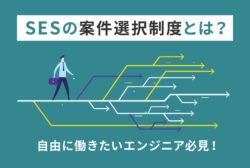
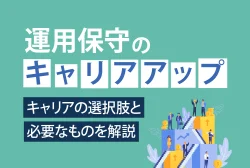

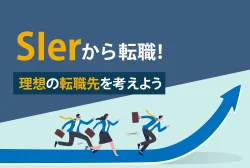
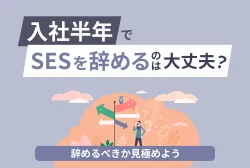
監修者コメント
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
プロフィールを見る
クラウドエンジニアとして“選ばれる存在”になるために必要な視点
クラウドエンジニアにとって、資格は「信頼される技術者」になるための裏付けになります。
ただし、資格はあくまで手段であり、その先にある実務経験やプロジェクトでの成果が本当の評価軸になります。
資格を選ぶ際は、自分の現在地だけでなく「どのような課題を解決できるエンジニアになりたいか」という視点を持つことが重要です。
どの分野で活躍したいかが明確になれば、目指すべき資格もおのずと決まります。
また、複数のクラウドを扱える“マルチクラウド人材”の需要も高まっており、将来的にはベンダーをまたいだ学習戦略も視野に入れるといいでしょう。