IT業界が派遣ばかりの理由と実態|自分に合う働き方を考えよう

目次
「そろそろ年収を上げたい」「今よりも成長できる環境に移りたい」と考えて求人を探してみたところ、派遣や客先常駐の募集ばかりが目についた方もいるかもしれません。
実際、IT業界では、広く浸透しており「IT業界は派遣ばかり」と感じるのも無理はないでしょう。
しかし、派遣や客先常駐という働き方には、マイナス面だけでなく、キャリア形成や収入アップにつながる側面もあります。
選ぶ企業や働き方次第で、自分に合ったキャリアパスを実現することも可能です。
本記事では、IT業界に派遣が多いとされる背景や構造を解説しながら、実際のキャリア形成の選択肢や、他の働き方の特徴も紹介します。
転職を機に、どのような働き方が自分の希望に合っているのかを整理し、より納得感のあるキャリア選択をするための参考にしてください。
IT業界は派遣ばかりって本当?
「IT業界は派遣ばかり」と感じている方は少なくありません。
実際、厚生労働省の調査によれば、IT企業の9割以上が派遣や客先常駐といった働き方を利用していると報告されています。
また、実態調査の結果を見ても、IT業界の派遣労働者の割合が23.1%と高めになっていることが分かりました。
日本の他産業と比較しても、IT業界は派遣労働者の比率が高く、この傾向は業界の構造的な要因と深く結びついています。
特に常駐型の案件が多くなる背景には、クライアント企業がシステム開発を外部委託しつつも、進捗や品質を自社内でコントロールしたいという意向があるためです。
このニーズに応える形で、SESや派遣のエンジニアが現場に常駐するケースが一般
的になっているのです。
参考:厚生労働省「働き方・休み方改善ハンドブック」「令和4年派遣労働者実態調査の概況」
IT業界が派遣ばかりの理由
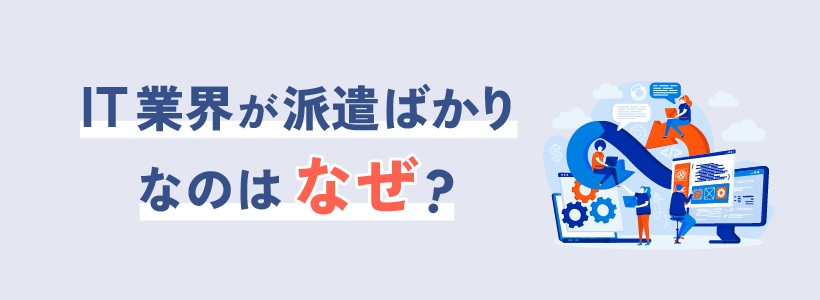
IT化が進む現代では、多くの企業が業務のデジタル化を進めており、エンジニアに対するニーズは年々高まっています。
ただし、全ての企業が自社でIT人材を正社員として抱える体制を整えられているわけではありません。
各企業の事情を鑑みて、必要なときに必要な人材を確保できる派遣や客先常駐の仕組みが重宝されてきた経緯があります。
結果として「IT業界は派遣が多い」と言われる状況が生まれているのです。
IT業界全体でエンジニアが不足している
IT業界では慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。
経済産業省の調査によると、人手不足が続き、2030年には最大で79万人のIT人材が不足すると予測されています。
全ての企業が必要なエンジニアを自社だけで確保し続けるのは、現実的に難しいといえるのです。
特に中小企業では、限られた採用リソースの中で優秀な人材を集めるのが困難で、その穴を埋める手段には派遣のような外部人材の活用が一般的です。
その結果、現場では多くのプロジェクトにおいて派遣エンジニアが不可欠な存在となっており、業界全体で派遣という働き方が広がる要因にもなっています。
参考:経済産業省「IT人材需給に関する調査」
必要な人員を確保しやすい
ITプロジェクトでは、案件の規模や内容に応じて必要となるエンジニアの人数やスキルセットが大きく異なります。
数が足りていても、実際には特定の技術や経験を持つ人材がおらず、プロジェクトが思うように進まないというケースも珍しくありません。
特に新しい技術や専門的な知識が求められる場面では、社内に該当する人材がいないこともあります。
そのような状況において、必要なスキルを持った人材を確保できる派遣の仕組みは、企業にとって有効な選択肢となっています。
迅速に対応できる
IT業界では、クライアントからの急な依頼や予期しないトラブルにより、短期間で人員を増やさなければならない状況が発生することがあります。
とはいえ、自社で人材を採用しようとすれば、募集から面接、内定、入社までに数週間から数ヶ月かかってしまうでしょう。
人材確保に時間を費やした場合、プロジェクトの遅延が発生するリスクも否めません。
そのようなときに活用されるのが派遣という仕組みです。
派遣会社側は、あらかじめエンジニアのスキルや経歴を把握しているため、企業の条件に合う人材をスピーディーにアサインできます。
採用にかかるコストや工数を抑えつつ、必要な戦力を即時に投入できるため、緊急対応が求められる現場では重宝されるのが派遣の特徴といえます。
受託開発が多い
多くの企業がクライアントから依頼を受ける受託開発を中心に事業を展開しており、安定した収益を確保するために複数の案件を並行して進めることも珍しくありません。
しかし、開発を受託している企業の多くは、慢性的な人員不足や限られた資金の中で運営しており、全ての人材を自社でまかなうことが難しいです。
また、IT業界には多重下請け構造が根付いており、上流工程から下流工程へと業務が分担されていく中で、下流に近づくほど派遣エンジニアの割合が増える傾向にあります。
このような業界の仕組みによって、開発現場では常に人手を外部に依存する構造が生まれ、結果的に「IT業界は派遣ばかり」という印象が定着したともいえます。
IT業界で派遣として働くメリットとデメリット
IT業界では派遣として働くエンジニアが多く、現場の第一線で活躍している人もいます。
しかし、派遣という働き方にはメリットとデメリットの両面があります。
これからIT業界で働こうと考えている方や、転職を検討しているエンジニアは、このメリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
派遣として働くメリット
派遣として働く場合、特定の企業に長く在籍するスタイルとは異なり、一定期間ごとに様々な現場を経験できるのが魅力です。
プロジェクトごとに開発手法や技術スタック、業務フローも変化するため、多様な実践経験を積むことができるでしょう。
こうした環境では、状況に応じた柔軟な判断力や応用力が自然と養われていきます。
また、勤務地や勤務時間、業務内容の選択肢が比較的豊富で、ライフスタイルの変化にも対応しやすいという特徴があります。
例えば子育てや介護、転居などのライフイベントが重なる時期でも、フルタイム勤務に縛られずに柔軟に働き続けることが可能です。
このように、スキルの習得と柔軟な働き方の両立を目指せる点は、派遣ならではの大きなメリットです。
派遣として働くデメリット
派遣として働く際には、事前に希望条件の確認や企業の雰囲気について情報共有を受けることができます。
しかし、実際の業務やチームとの相性は働いてみないと判断が難しいです。
仮に理想的な職場に出会えた場合でも、派遣契約には期間の定めがあるため、一定のタイミングでその現場を離れなければならないケースも考えられます。
また、同じ企業に長く在籍できないことによって、特定の分野を深掘りする機会が限られてしまう場合もあります。
職場が変わるたびに新しいスキルや業務内容への対応が求められ、それを負担に感じる人がいるのも事実です。
短期間で幅広い経験を積める点は派遣の強みといえますが、専門性を一点集中で伸ばしたい人にとっては、必ずしも適した働き方とはいえないのです。
派遣ばかりのIT業界でのキャリアパス
IT業界は派遣という働き方が広く普及しているものの、キャリアの選択肢が限られているわけではありません。
実務経験を積みながら、自分の強みや志向に応じて次のステップを柔軟に描けるのが、この業界の大きな特徴です。
例えば、特定の技術領域に特化して専門性を深めていくスペシャリストの道や、チームやプロジェクトをまとめるマネジメント職を目指す道があります。
他にも、派遣を通じて多様な現場を経験したうえで、フリーランスとして独立し、自分のペースで動ける働き方を選ぶ人もいます。
IT業界全体が成長を続けている今、キャリアの選択肢は広がっており、自分の価値観やライフスタイルに合った働き方を見つけることが重要です。
働く環境が多様化する中で、方向性を見極めながら、自分にとって納得のいくキャリアパスを設計していく姿勢が求められます。
監修者コメント
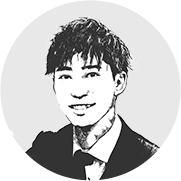
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
キャリアの“軸”はスキルよりも、どのような課題を解決したいかで決まる
派遣からスタートして、スペシャリストやマネジメント、フリーランスといった道へ進むのが王道です。
しかし、キャリアを形づくる本質は「何ができるか」だけではありません。
「どの課題に取り組みたいか」「どのような場面で自分の力を使いたいか」といった“軸”の部分が、将来の方向性を決めていくのです。
例えば、インフラ系のスキルを持つ人が「社内全体のパフォーマンス改善に貢献したい」と感じたとき、社内SEやSREなど“組織に関わる役割”を志すこともあります。
逆に「顧客の課題解決やサービス企画にワクワクする」と気づいたなら、プリセールスやPM、さらにPdMなどの選択肢も視野に入ります。
大切なのは、スキルや職種といった肩書きにとらわれすぎず「自分がどんなテーマに熱量を持てるか」に目を向けることです。
IT業界は柔軟に働けるからこそ、自分の中にある“解決したい問い”を明確にしておくことで、仕事への納得感やキャリアの選択の軸が定まります。
派遣ばかりのIT業界で派遣を避けられる転職先
派遣という働き方は、今のIT業界にとって重要な役割を担っており、柔軟な人材配置や即戦力の確保という点で多くの現場で活用されています。
ただし、安定した職場で長期的にキャリアを築きたい方にとっては、相性が合わないと感じることもあるでしょう。
働く環境が短期間で変わることや、スキルアップに関して不安や不満を抱く場合は、あらかじめ派遣以外の働き方を視野に入れて企業選びをすることが大切です。
正社員として社内開発に携わるポジションや、自社サービスを運営している企業など、派遣を避けたキャリア設計も十分に可能です。
SIer
SIer(エスアイヤー)とは「システムインテグレーター」の略称です。
企業や団体の業務に合わせたシステムの設計・開発・運用などを一貫して請け負うIT企業を指します。
中でも、大手SIerのようにクライアントから直接案件を受注する“元請け”の企業は、自社内でプロジェクトを完結できる体制を持っているのが特徴です。
そのため、社員が他社に派遣されることはほとんどなく、外部人材を派遣する形で受け入れる側に回ることが多くなります。
正社員で入社すれば、基本的には自社内の業務に腰を据えて取り組める環境が整っているといえます。
安定性を重視してキャリアを築いていきたいエンジニアにとっては、こうした大手SIerへの転職も魅力的な選択肢の1つです。
自社開発企業
自社開発企業とは、自社で企画・開発・運用までを一貫して行っているIT企業のことであり、基本的に他社へ派遣される働き方は発生しません。
自社のサービスを継続的に改善していく体制が中心となっているため、エンジニアも自社オフィスやリモート環境の中で腰を据えて業務に取り組むことができます。
必要に応じて営業や導入支援などでクライアント先を訪問することはあっても、一時的な対応にとどまり、客先常駐や派遣といった形にはなりません。
開発環境や働く場所の安定性を重視したい方にとって、自社開発企業は派遣のない働き方を実現しやすい選択肢です。
スキルの向上だけでなく、チームで中長期的にサービスを育てたいと考えるエンジニアにとっても魅力的な環境といえます。
社内SE
社内SEは、自社の情報システムやITインフラを維持・管理・改善する職種であり、外部案件ではなく自社内の業務効率化やシステム運用をサポートします。
近年では、業界を問わずIT化やDX化が進んでおり、企業が社内SEを雇用するケースが増えてきました。
派遣や客先常駐のような働き方にはならず、あくまで社内の業務改善や社員からの問い合わせ対応、システム導入・運用といった業務に集中できる環境といえます。
業務内容の幅は企業によって異なりますが、社内のIT環境を支える、必要不可欠な存在です。
ITスキルを活かしつつも、勤務場所を変えずに長期的に働きたいと考えるエンジニアにとっては、魅力的な選択肢といえます。
派遣で働くことを迷っているなら「SES企業」も選択肢の1つ
派遣という働き方に不安を感じている方は、SES(システムエンジニアリングサービス)企業も検討してみましょう。
どちらも「自社の社員が他社で業務にあたる」という点では共通していますが、契約形態や働き方には違いがあります。
| SES会社 | 派遣会社 |
|---|---|
| SES契約 派遣契約 請負契約 | 登録型派遣 常用型派遣 |
派遣の場合は派遣先の企業が直接指示を出す形になりますが、SESでは自社の指揮命令系統のもとで働くことが基本です。
スキルアップの方向性やキャリア形成も、所属する企業の方針によって異なるため、自分に合った働き方を見つけるうえで、契約形態の理解は欠かせません。
一見すると似ているように見える派遣とSESですが、その実態は大きく異なることもあるのです。
後悔のない選択をするためにも、まずは「どう違うのか」を知ることから始めましょう。
SESと派遣についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
合わせて読みたい
まとめ
IT業界では、派遣や客先常駐といった働き方が広く活用されています。
その背景には、慢性的なIT人材不足や、プロジェクト単位での柔軟な人員確保ニーズ、さらには多重下請けといった業界特有の仕組みが関係しているといえます。
派遣は、様々な現場を経験でき、自分の生活スタイルに合わせやすい働き方です。
一方で、契約期間が定められているため長期的な安定性に欠けたり、特定分野の専門性を深めづらいと感じる人もいるでしょう。
大切なのは、自分にとって無理のない環境や条件を見極めながら、納得のいくキャリアの形を選んでいくことです。
弊社ESESは、SES企業としてエンジニアが長く安心して働けるよう、各種制度を整えています。
例えば「案件選択制度」があることで、自身の希望やスキルに応じてプロジェクトを選べる仕組みになっています。
また、単価評価制度や高還元率により、成果が正当に反映される納得感のある働き方を実現しています。
スキルアップやキャリア形成に関する支援も充実しています。
「今の働き方に迷いがある」
「もっと成長できる場所で挑戦したい」
クラウドやインフラといった成長分野に関わりながら、経験を重ね、年収アップも着実に目指していける仕組みが整っています。
理想のキャリアを描く第一歩を、ESESで踏み出してみませんか?
まずは募集要項をご覧いただき「なりたい自分」の実現に向けて一緒に進んでいきましょう。




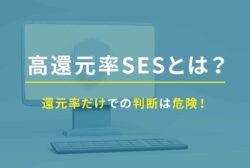
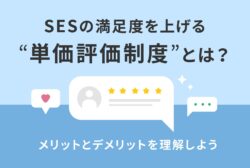
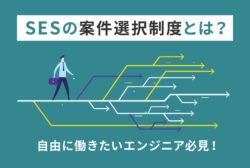

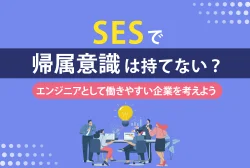
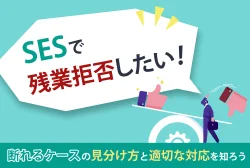
監修者コメント
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
プロフィールを見る
現場経験を“再現可能なスキル”に変える意識を持つ
派遣で多様な現場を経験できるのは大きな強みですが「数多くの現場に行った」という事実だけでは市場価値が伝わりづらいのが現実です。
例えば、A社ではWindowsサーバ構築、B社ではヘルプデスク対応、C社では社内ネットワークの保守など、現場ごとに業務がバラバラになることは少なくありません。
そこで重要になるのが「どのような課題があり、どう解決したか」を言語化しておくことです。
業務日報や振り返りメモなどに、自分なりの工夫や気づきを残しておくと、それが“再現可能なスキル”となり蓄積されます。
技術力に加えて、業務全体の流れをどう捉えたか、関係者とどう連携したかといった視点も、次の現場で活かせる強力な武器になるでしょう。
派遣という働き方は「経験を広げるチャンス」でもあります。
その意識の差が、数年後のキャリアを大きく分けるでしょう。