アプリケーションエンジニアが「やめとけ」と言われる理由|やりがいと向いてる人の特徴も解説
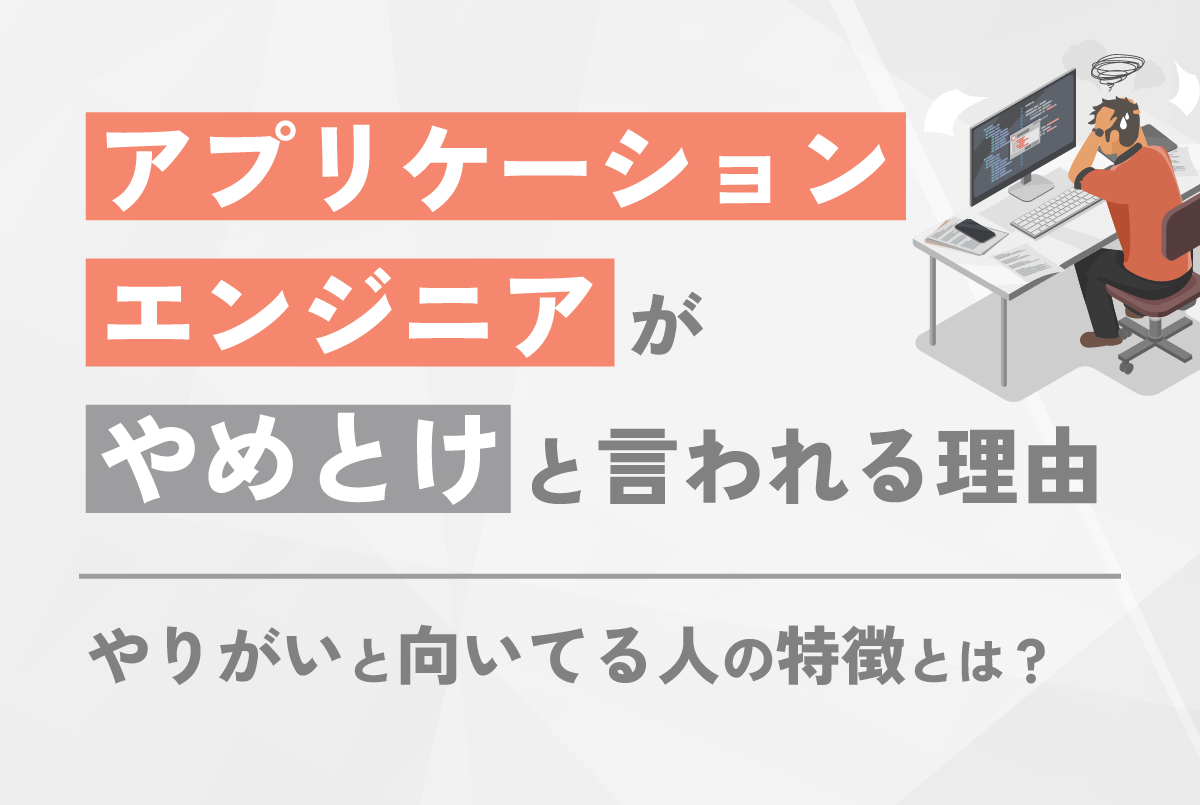
目次
「アプリケーションエンジニアはやめとけ」という言葉を耳にして、転職を迷っている方もいるのではないでしょうか。
実際には、ユーザーの課題を直接解決しながら収入アップも狙える、やりがいの大きい仕事です。
本記事では「やめとけ」と言われる背景を整理しつつ、キャリアを伸ばせる魅力や年収面のメリットを解説します。
最後に、アプリケーションエンジニアに向いている人の特徴も紹介。
自分に合う働き方かどうか判断する材料として活用してください。
やめとけと言われる「アプリケーションエンジニア」とは?
アプリケーションエンジニアとは、業務システムやWebサービス、スマホアプリなど、ユーザーが操作する機能そのものを開発・改善していく職種です。
ユーザーの利便性に直結する部分を担当するため、技術だけでなく要件理解や設計力、時には折衝能力も求められます。
アプリケーションエンジニアの仕事内容や必要なスキルを詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
合わせて読みたい
アプリケーションエンジニアの仕事内容
アプリケーションエンジニア(AE)は、アプリケーションの開発に関する工程全般を担う職種です。
業務内容は、以下のような工程が挙げられます。
- システムの要件定義・設計
- プログラム開発
- 動作テスト
- 運用保守
企業によってはプログラマーと兼任することもあり、システムエンジニア(SE)とほぼ同じ役割を担うケースも少なくありません。
特定のフェーズに特化したり、全行程に関わったりと、プロジェクトの規模や体制によって関わる範囲は異なります。
柔軟に対応することが求められる一方で、上流から下流まで一貫して関われる点は大きな特徴です。
アプリケーションエンジニアが開発するもの
アプリケーションエンジニアが開発する対象は多岐にわたりますが、大きく分けて3つの種類に分類されます。
- スマホ用アプリケーション
- Webアプリケーション
- 業務系アプリケーション
1つ目は、スマートフォン向けのアプリケーションです。
iOSやAndroidで動作するアプリを開発し、ユーザーの利便性や体験を高めることが求められます。
2つ目は、Webアプリケーションです。
ブラウザ上で利用されるサービスや業務ツールなどが該当し、フロントエンドとバックエンドの両面から設計や実装を行う場合もあります。
3つ目は、業務系アプリケーションです。
主に企業内で利用されるシステムで、業務効率化やデータ管理を目的とした開発が中心です。
どの分野も技術的な知識は必要ですが、求められるスキルや開発手法、ユーザーとの関わり方は異なります。
アプリケーションエンジニアを目指す際は、どの領域に興味があるか、自分がどのようなサービスを作りたいかを明確にしておくことが大切です。
アプリケーションエンジニアが「やめとけ」と言われる理由
アプリケーションエンジニアは、ユーザーの利便性に直結する機能を担う重要なポジションです。
しかし、以下のような「やめとけ」という声が出るのも事実です。
- 業務量が多い
- 長時間労働や休日出勤が多い
- 予期せぬ事態が発生する
- 学習し続けなければいけない
これからアプリケーションエンジニアを目指す人にとっては、どのような点が大変だと感じられているのかを知っておくことは重要です。
ここからは、実際に「やめとけ」と言われる具体的な理由について順に見ていきましょう。
業務量が多い
アプリケーションエンジニアが「やめとけ」と言われる理由の一つに、業務量の多さが挙げられます。
そもそもIT業界全体で慢性的な人材不足が続いており、アプリケーションエンジニアも例外ではありません。
プロジェクトの進行や保守対応、トラブル処理などを少人数で回すケースも多く、どうしても一人当たりの負担が大きくなりやすい状況です。
また、開発以外にも要件整理やテスト、設計修正など複数のタスクを同時並行でこなす場面もあり、時間的な余裕が取りにくくなることもあります。
人手不足の中でもプロジェクトは止められないため、短納期や急な仕様変更などにも対応しなければなりません。
参考:経済産業省「IT人材育成の状況等について」
長時間労働や休日出勤が多い
納期や品質を守るために、限られた時間内で多くの作業をこなす必要があるのがアプリケーションエンジニアの現場です。
開発の終盤やトラブル対応など、スケジュールがひっ迫する局面では休日出勤を求められることも少なくありません。
特にリリース直前は想定外の修正が発生することも多く、計画通りに作業が進まないリスクも伴います。
こうした状況に拍車をかけているのが、業界全体に広がる人材不足です。
本来チームで分担すべき業務が、一人のエンジニアに集中することもあり、結果として長時間労働が常態化しやすくなっています。
そのため、プライベートの時間が削られ、心身ともに負荷を感じやすくなります。
企業によって状況は異なるものの、こうした働き方に悩む声が一定数あるのは事実です。
予期せぬ事態が発生する
アプリケーション開発の現場では、あらかじめ決められた計画通りにすべてが進行するとは限りません。
たとえ丁寧に要件定義やスケジュール管理を行っていたとしても、予期せぬトラブルが起きるのはよくあることです。
特に、人手不足によって一人のエンジニアが多くのタスクを抱えている状態では、急な変更や不具合が発生したときの影響が大きくなりがちです。
例えば、顧客からの要望による仕様変更や、開発途中で見つかるバグ対応、サーバーやネットワークの障害などが挙げられます。
こうした事態が重なると、通常の業務時間内では収まらず、やむを得ず残業や休日作業が必要になるケースも少なくありません。
負荷の高い工程を任される立場である以上、柔軟に対応しながらも精神的な余裕を保つことが大切です。
学習し続けなければいけない
アプリケーションエンジニアとして働くうえで避けて通れないのが、継続的な学習です。
IT業界は変化のスピードが非常に速く、新しい技術や開発手法、ツールが次々と登場しています。
特にアプリケーション開発では、ユーザーの求める機能やUXが高度化しており、それに対応するためには新しい知識のインプットが欠かせません。
一度習得したスキルに満足してしまうと、気づかないうちに現場の要件や市場のニーズとズレが生じる可能性もあります。
日々の業務と並行して、書籍やオンライン講座での学習、技術記事のチェック、実際の手を動かした検証など、自発的に取り組む姿勢が求められます。
こうした継続的な学習を負担に感じて「やめとけ」と言う人もいるのです。
「やめとけ」と言い切れないアプリケーションエンジニアのやりがい
アプリケーションエンジニアは「やめとけ」と言われる理由があるのも事実ですが、それだけで判断してしまうのは早計です。
業務量の多さやスケジュールの厳しさ、学習の継続など大変な側面はありますが、その一方でやりがいや達成感も大きいです。
課題はあるものの、それ以上にやりがいを感じられる瞬間があるからこそ、多くのエンジニアがこの仕事に誇りを持って取り組んでいます。
ここからは、アプリケーションエンジニアとして働く中で感じられる、代表的なやりがいについて紹介していきます。
給与水準が高い
アプリケーションエンジニアの仕事には責任や負荷が伴う一方で、その分給与水準が高い傾向にあります。
厚生労働省が提供する職業情報サイト「jobtag」のデータを見てみましょう。
スマートフォン向けアプリケーション、パッケージソフトの開発を行うエンジニアの平均年収は、それぞれ557万6,000円とされています。
これは他のエンジニア職と比較しても高い水準であり、スキルや経験を積むことで年収アップが十分に見込める職種です。
また、実務の中で新しい技術を習得しやすい環境にあるため、スキルアップと年収の向上が直結しやすい点も特徴の一つです。
努力が収入に反映されやすい分野であることから、成長意欲の高い人にとっては大きなモチベーションにつながるでしょう。
参考:厚生労働省「職業情報提供サイト(jobtag)」「ソフトウェア開発(パッケージソフト)」
結果が見えやすい
アプリケーションエンジニアの仕事は、成果が目に見えやすいという特徴があります。
自分が開発に携わったアプリケーションが、実際に世の中で使われるため「自分の仕事が誰かの役に立っている」という実感を得やすいです。
ユーザーからのレビューや評価、社内外のフィードバックがダイレクトに届くこともあり、自分のアウトプットに対して反応を受け取れる点も魅力の一つです。
ときには改善の要望や不具合の報告がある一方で「便利になった」「助かっている」といった前向きな声を受け取ることもあり、モチベーションの維持につながります。
努力の成果が数字やユーザーの声として返ってくるため、手ごたえを感じながら継続的に取り組むことができるのは大きなやりがいです。
仕事とプライベートの両立がしやすい
アプリケーションエンジニアは、在宅勤務と相性の良い職種の一つです。
インターネット環境と開発環境が整っていれば、自宅での作業が可能なため、場所にとらわれずに働ける柔軟さがあります。
特に、子育て中の人や家庭の時間を大切にしたい人にとっては、仕事とプライベートの両立がしやすい環境といえるでしょう。
在宅であれば決められた時間に出社する必要がなく、自分の生活リズムに合わせて働けるのも大きなメリットです。
また、通勤時間が不要になることで体力的・精神的な負担も軽減され、結果として仕事のパフォーマンスが向上することも期待できます。
自由度の高い働き方を求めている方にとっては、アプリケーションエンジニアは魅力的な選択肢となるでしょう。
在宅で働けるエンジニア職についてさらに知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
合わせて読みたい
「アプリケーションエンジニアはやめとけ」と言われない人の特徴

アプリケーションエンジニアは「やめとけ」と言われる要素がある一方で、大きなやりがいや成長機会がある職種です。
全ての人に合う仕事ではないものの、性格や得意分野によってはスムーズに適応し、長期的に活躍できるケースも少なくありません。
ここからは、実際に「アプリケーションエンジニアに向いている」と言える人の特徴について詳しく見ていきましょう。
論理的思考が得意
アプリケーションエンジニアの仕事は、論理的な思考力を土台に成り立っています。
アプリを開発する際には、まず要件を正確に整理し、どのような仕様に落とし込むかを明確にする必要があります。
開発が進む中では、予期せぬエラーや仕様上のズレが発生することもあり、その原因を一つずつ丁寧に切り分けて特定していく作業が欠かせません。
また、プログラム自体が論理の積み重ねで構成されているため、バグ修正や機能改善といった作業においても、論理的な視点が重要です。
仕組みを深く理解しながら課題に向き合える人にとっては、大きなやりがいを感じられる分野といえるでしょう。
新しい技術に興味がある
アプリケーションエンジニアとして活躍するうえで、新しい技術に対する関心や好奇心は欠かせない要素です。
IT業界は技術の進化が非常に速く、数年前の知識やスキルだけでは対応しきれない場面も多いです。
例えば、新しいプログラミング言語やフレームワーク、クラウドサービスなどは次々と登場し、現場で求められる技術も変化し続けています。
こうした環境の中で、常にアンテナを張って情報をキャッチし、自主的に試して学ぶ姿勢がある人は、自然とスキルの幅が広がっていきます。
技術に興味を持ち、楽しみながら吸収できる人ほど、エンジニアとしての市場価値も高まりやすく、キャリアアップのチャンスをつかみやすいです。
作業をコツコツ続けられる
アプリケーション開発の現場では、派手な成果物だけでなく、日々の地道な作業こそがプロジェクトの品質を支えています。
要件を確認しながら細かい仕様を詰めていく工程や、動作検証のためのテスト作成、バグの洗い出しと修正といった作業は、いずれも集中力と粘り強さが求められます。
エラーを一つひとつ取り除いていくプロセスは、成果がすぐに見えにくいことも多く、途中で気持ちが切れてしまう人も少なくありません。
そうした場面でも、コツコツと作業を積み重ねることができる人は、開発チームにとって非常に信頼される存在になります。
効率やスピードも大切ですが、根気強く正確に取り組める力は、アプリケーションエンジニアにとって重要な適性の一つです。
チームでのコミュニケーションが得意
アプリケーションの開発は、設計から実装、テストに至るまでを複数のエンジニアや関係者が連携して進めていくのが一般的です。
一人で完結する仕事ではないため、チームでのコミュニケーション能力は極めて重要なスキルの一つとなります。
自分の考えや進捗状況を正確に伝える力に加えて、相手の意見をくみ取り、必要に応じて調整やすり合わせを行う姿勢が求められます。
また、チーム全体のスケジュールや状況を意識しながら、適切なタイミングで報告・連絡・相談ができる人は、プロジェクトに大きく貢献する存在となるでしょう。
トラブルや認識のズレを未然に防ぐうえでも、積極的にコミュニケーションを取る習慣がある人は周囲からの信頼も集めやすくなります。
こうした力を備えている人は、チーム全体のパフォーマンスを高める重要な役割を果たすことができるはずです。
ユーザー目線で考えられる
アプリケーション開発においては、ユーザーにとって使いやすい設計になっているかどうかが重要なポイントです。
いくら機能が豊富でも、操作が複雑だったり、UIが直感的でなかったりすると、ユーザーの満足度が下がり、継続して使われなくなる可能性があります。
そのため、エンジニアには「作り手」としての視点だけでなく「使い手」の立場に立った思考が求められます。
実際にユーザーがいつ、どのような目的でアプリを利用するのかを想像しながら、設計や改善に取り組める人は、プロダクトの品質を高められるでしょう。
細かな気づきや使い勝手への配慮ができるエンジニアは、チーム内でも重宝され、ユーザーからの評価にも直結します。
ユーザー目線を持てるかどうかが、アプリケーションエンジニアとしての実力を左右する要素の一つといえます。
柔軟な対応ができる
アプリケーション開発は計画通りに進むことばかりではなく、予期せぬトラブルや仕様の変更が発生することも少なくありません。
エラーの原因がなかなか特定できなかったり、クライアントから急な修正依頼が入ったりと、現場では想定外の対応が求められる場面が頻繁にあります。
予想外の出来事が発生した際にパニックにならず、視点を切り替えて別の角度から解決策を考えられる柔軟性は大きな強みとなります。
開発環境や要件が流動的なプロジェクトにおいても、前向きに対応し、変化を受け入れられる人は長く活躍しやすい傾向があります。
柔軟に考えながら行動できる力は、アプリケーションエンジニアとして成果を出すために欠かせない資質の一つです。
監修者コメント
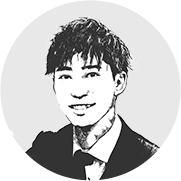
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
自分の担当領域を“横に広げる意識”が信頼を生む
アプリケーションエンジニアとして長く活躍するためには「自分の担当タスクだけをこなす」というスタンスから一歩踏み出すことが大切です。
“横に広げる”とは、自分の工程だけでなく、その前後のプロセスである設計、テスト、フロントやインフラの動きにも関心を持ち、全体の流れを意識する姿勢を指します。
例えば、設計書を読んで曖昧な点に気づいたら、早めにQAを整理しておく。
あるいは、自分が担当するAPIの仕様を確認しながら「この仕様だとフロント側の実装が複雑になりそう」と共有する。
このように、チームの作業効率や品質に貢献する行動が取れると、評価は大きく変わります。
こうした姿勢は、単なる実装担当ではなく「プロジェクト全体を理解し、改善提案ができる人材」として認識されやすくなります。
その結果、自然と信頼も集まり、単価や役割にもプラスに働くでしょう。
「やめとけ」と言われるアプリケーションエンジニアに関するよくある質問
アプリケーションエンジニアは「やめとけ」といったネガティブな意見が挙がることもありますが、それが全ての人に当てはまるわけではありません。
職場環境やプロジェクトの状況、そして自身の適性や考え方によって、大変さの感じ方は人それぞれ異なります。
そこでここでは、アプリケーションエンジニアに関してよく寄せられる疑問や不安に対し、具体的な視点から回答を紹介していきます。
転職やキャリアチェンジを検討している方は、判断材料として役立ててください。
Q1.アプリケーションエンジニアの需要・将来性はあるの?
アプリケーションエンジニアの将来性について不安を感じる人もいるかもしれませんが、結論から言えば需要は高まり続けています。
現在問題となっているIT業界全体の慢性的な人材不足は、今後も続くといえます。
IT技術は社会全体に広がりながら発展を続けており、それに伴ってITエンジニア全体のニーズも高まってきました。
特に最近では、企業の業務効率化やサービス改善を目的としたDX(デジタルトランスフォーメーション)が急速に進んでいます。
その中で、アプリケーションエンジニアの果たす役割も大きくなっています。
新しいビジネスモデルや業務システムを支えるアプリケーション開発は、今や企業活動の中核を担う分野の一つです。
そのため、今後も安定した需要が見込まれます。
変化の激しい時代だからこそ、技術力を持ったエンジニアの価値はさらに高まるでしょう。
Q2.アプリケーションエンジニアのキャリアパスは?
アプリケーションエンジニアとしてのキャリアは、段階的にステップアップしていきます。
最初は既存システムの運用や保守といった、比較的難易度の低い業務からスタートすることが多いです。
その後、プログラムの実装やテストといった開発業務を通じて実務経験を積み、徐々に要件定義や設計といった上流工程を任されるようになります。
設計から実装、テスト、運用まで、アプリ開発の一連の流れを理解し、自走できるようになればキャリアの選択肢は広がるでしょう。
例えば、技術を極めてスペシャリストとして活躍する道もあれば、PM(プロジェクトマネージャー)を目指す人もいます。
他にも、PL(プロジェクトリーダー)としてチームをまとめるポジションを目指すことも可能です。
自分の強みや志向に合わせて、キャリアの方向性を柔軟に選択できるのがアプリケーションエンジニアの魅力です。
まとめ
アプリケーションエンジニアは「やめとけ」と言われる理由があるのも事実です。
その背景には、業務量の多さや予期せぬトラブル、長時間労働などの厳しさが存在します。
しかし、それらのデメリットに加えて、アプリケーションエンジニアの仕事には大きなやりがいもあります。
自分の手で作り上げたものがユーザーに使われ、直接的な反応を得ることができるのは、アプリケーションエンジニアならではのやりがいです。
また、IT化が進み、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速する中で、アプリケーションエンジニアの需要は今後さらに高まることが予想されます。
そのため、アプリケーションエンジニアとして活躍したいと考えているのであれば、これから目指す価値のある職種といえるでしょう。
弊社ESESは、システムエンジニアリングサービス(SES)企業です。
エンジニアが自分に合った案件を選べる案件選択制度や透明性や納得度の高い報酬を得られる単価評価制度、高還元率を実現しています。
また、キャリアアップやスキルアップの支援を行い、経験が少ない方でも安心して働ける環境が整っています。
「アプリケーションエンジニアとして活躍したいけれど不安がある」という方にも、弊社ではキャリアプランに沿ったサポートも可能です。
経験を積みながら、アプリケーションエンジニアとしてのスキルを伸ばし、希望のキャリアを築いていきましょう。


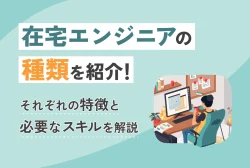


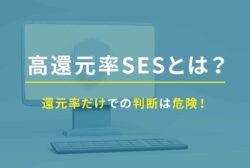
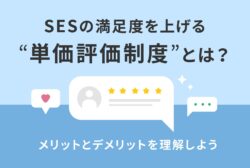
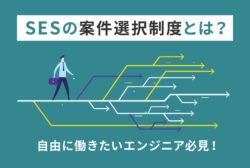
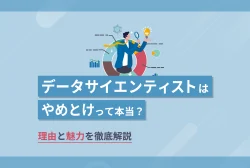
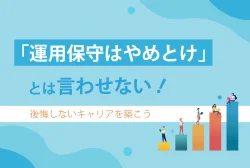
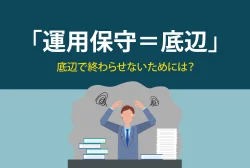

監修者コメント
白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO
プロフィールを見る
視野の広さが収入につながる
アプリケーションエンジニアとして年収を上げるには、技術力だけでなく、プロジェクト全体を見渡す視野や、チームに貢献する姿勢が重要です。
例えば、要件が曖昧な段階で放置せず、仮の実装を提案することで、関係者の認識を揃え、議論を前に進めることができます。
こうした行動は、品質の高いアウトプットを早期に生み出すきっかけとなり、チームからの信頼も高まります。
信頼が蓄積されれば、上流工程への関与やリーダー的なポジションを任されやすくなり、評価にもつながるのです。
結果として、年収アップやキャリアの幅を広げることが現実的になっていくでしょう。